Twitter(X)のアルゴリズムとは?仕組み・最新動向と伸ばすための攻略法【2025年最新版】
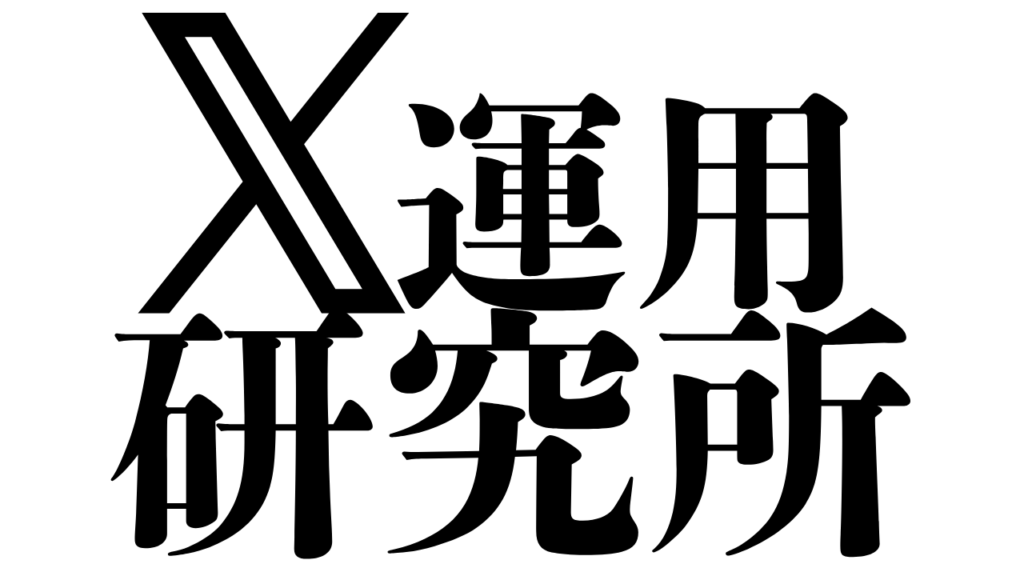
X運用研究所は、Momemtum Marketingが運用する、X運用ノウハウを体系的に学べるオウンドメディアです。
SNSを“ただの発信手段”から、“価値を生み出す武器”へ。
このメディアは、すべてのXユーザーの可能性を広げる研究と実践のプラットフォームです。
X道場 ~for Bussiness~
X(旧Twitter)は、単なる情報発信ツールではなく、大きな成果をもたらす強力なマーケティングプラットフォームです。
弊社のサービス「X道場」では、フォロワーを増やすだけではなく、ビジネス目標に直結する本質的なXマーケティングを実践します。企業様から一般ユーザーまで幅広く使用いただけるプラットフォームです。


Twitter Xのアルゴリズムとは?基本を理解する
Twitter改め「X」では、ユーザーに表示される投稿(ツイート)の順序や内容はすべて独自のアルゴリズムによって決定されています。
アルゴリズムとは、情報を取捨選択し並べ替えるためのルール・仕組みのことです。Xのタイムライン上では、単純に新しい順で投稿が並ぶだけではなく、「この投稿はあなたに合いそうだ」とAIが判断したものが優先的に表示されるようになっています。
つまり、各ユーザーの興味や関心に合わせてタイムラインがパーソナライズされているのです。
このアルゴリズムでは、ユーザーの過去の閲覧履歴や日々のアクション(「どんな投稿にいいねしたか」「誰をフォローしているか」「よくリポストしている投稿は何か」など)に基づいて関心が高いと判断された投稿が選ばれ、自動的に表示されます。
興味・関心に合ったポストを表示することで、ユーザーのエンゲージメント(反応)やタイムライン上での滞在時間を伸ばす狙いがあります。
実際、アルゴリズム経由で表示される投稿がユーザーにとって魅力的であればあるほど、より多くの「いいね」やリプライが発生したり、長く投稿を読んでもらえたりするため、プラットフォーム全体の活性化につながるのです。
アルゴリズムが果たす役割を理解するため、まずフォロー中タイムラインとおすすめタイムラインの違いを押さえておきましょう。
「フォロー中」タブでは、自分がフォローしているアカウントの投稿が時系列順(新着順)に表示されます。
それに対して「おすすめ」(For You)タブでは、フォローの有無に関わらずアルゴリズムが選び出した投稿が表示されます。
X社によれば、おすすめ表示される投稿はフォロー中ユーザーからの投稿とフォロー外ユーザーからの投稿がおおよそ半々になるよう調整されており、数億件の候補から約1500件程度のツイートが抽出されてタイムラインに並ぶ仕組みです。
したがって「おすすめ」タブでは、普段フォローしていないアカウントのツイートや話題も積極的に目に入るようになります。
一方、「フォロー中」タブでは自分のタイムラインを自分のフォロー範囲内に限定できるため、目的に応じて両者を使い分けることができます。
では、アルゴリズムが投稿を評価する指標にはどのようなものがあるでしょうか。
基本的にはユーザーの興味関心との関連度に加え、「エンゲージメント(ユーザーからの反応)」「閲覧時間(滞在時間)」「新しさ(鮮度)」といった要素が重視されます。
具体的には、投稿に付いたいいねやリポストの数、リプライ(返信)の量などは「どれだけその投稿が人気か」を示す重要なシグナルとなります。
また、単なるクリック数やいいね数だけでなく、投稿に対してユーザーがどれだけ長く画面に留まったか(スクロールを止めて読んだか)やリンクを開いたかどうかも評価に含まれます。
ユーザーがしっかり内容を読んだ投稿は「関心度が高い」とみなされ、より多くの人に表示されやすくなる傾向があります。
さらに、各ユーザーごとの興味分野にマッチした内容かどうか(関連性の高さ)も重要です。
例えばビジネスに関する投稿ばかり普段見ているユーザーには、ビジネス系の話題が優先表示される、といった具合に、その人ごとの関心に沿ったパーソナライズが行われています。
こうしたアルゴリズムの基本を理解すると、なぜ自分の投稿がタイムライン上でどの程度露出するのか、その背景が見えてくるでしょう。
Xでは2023年3月にアルゴリズムの一部がオープンソース化され公開されました。
それによりアルゴリズムの仕組みが徐々に明らかになり、「どのような投稿がおすすめ表示されやすいか」が以前よりも把握しやすくなっています。
アルゴリズム公開後、イーロン・マスク氏は「ユーザーからの提案をもとに24〜48時間ごとにおすすめアルゴリズムを更新していく」と述べ、絶えず改善が図られていることを強調しました。
つまりアルゴリズムは固定的なものではなく、ユーザー体験を高めるために継続的にアップデートされている点も押さえておきましょう。
アルゴリズムが果たす役割|投稿の表示順とおすすめ表示
Xのアルゴリズムは、膨大な投稿の中から「ユーザーにとって興味深く関連性の高いポスト」を選び出し、各ユーザーのタイムラインに届ける役割を担っています。
具体的には、まず候補となるツイート群の中からスコアの高い投稿を抽出(候補ソーシング)し、機械学習モデルによってランク付けし、不適切な投稿や既に見た投稿をフィルタリングした上で、フォロー情報や広告ツイート等とミキシングして表示させています。
最終的にユーザーのタイムラインに表示される投稿は、こうした複数段階のプロセスを経て決定されます。
アルゴリズムが賢く情報を取捨選択しているおかげで、ユーザーは自分の興味にマッチしたツイートを効率よく楽しむことができるのです。
特に「おすすめ」タブでは、アルゴリズムの働きが顕著です。
自分がフォローしていないアカウントからの投稿であっても、内容的に関連が高かったり多くの人が反応して人気となっているツイートは、おすすめ経由で表示される可能性があります。
例えば自分と似た嗜好を持つユーザーが多数「いいね!」している投稿は、アルゴリズムが「あなたも興味を持つかもしれない」と判断し、あなたのタイムライン上位に出てくることがあります。
逆に言えば、あなたの投稿もフォロワー以外の多くのユーザーに届けられるチャンスがあるということです。
アルゴリズムは単にフォロー関係だけでなく、ユーザー同士の繋がりや行動パターンを分析して「誰にそのツイートを見せるか」を決めているのです。
このようにXのアルゴリズムは、タイムライン上の投稿順序や露出範囲を動的にコントロールする存在です。
もしアルゴリズムが存在せず時系列の投稿だけであれば、1日に数百万件とも言われる膨大なツイートに埋もれてしまい、多くのユーザーは重要な情報を見逃してしまうでしょう。
しかし実際にはアルゴリズムが各投稿にスコアを付け、誰にとって有益か・興味深いかを判断して取捨選択してくれるおかげで、ユーザー体験が最適化されているのです。
「なぜ自分のタイムラインによく知らない人の投稿が表示されるのか?」と思ったことがある方もいるかもしれませんが、それもアルゴリズムがあなたの興味に合わせて見込みのある情報をレコメンドしている結果と言えます。
「フォロー中」と「おすすめ」タブの違い
Xではタイムラインの表示モードとして「フォロー中」と「おすすめ」の2つのタブが用意されています。この2つは表示される投稿の選ばれ方が根本的に異なります。
- 「フォロー中」タブ: 自分がフォローしているアカウントの投稿のみが、投稿時間の新しい順に表示されます。基本的にリアルタイムに近い形でタイムラインが更新されていき、アルゴリズムによるランキングは行われません(広告やプロモーション投稿を除く)。見逃し防止のため、過去の未読ツイートが多少優先表示されるケースはありますが、基本原則は時系列順です。タイムラインを自分のフォロー範囲の情報だけで構成したい場合や、新着を漏れなくチェックしたい場合に適しています。
- 「おすすめ」タブ(For You): フォロー関係に関わらず、アルゴリズムが「このユーザーにはこの投稿が合いそうだ」と判断したツイートがスコア順に並んで表示されます。フォロー中のアカウントのツイートも表示されますが、それ以外のアカウントからの投稿や話題も含まれる点が大きな特徴です。おすすめタブでは、抽出されたツイートのうち約半分はフォロー外からの投稿になるよう調整されており、自分ではまだフォローしていない有益な情報源との出会いが提供されています。ここではアルゴリズムが各投稿の関連度やスコアを計算し、「今このユーザーに見せるべき上位数十件」を選び出してタイムラインを構成します。そのため、自分がフォローしている人の投稿であってもエンゲージメントが低かったり関連性が薄いと判断されたものは下位に埋もれ、逆にフォロー外でも話題性が高く自分好みだと判断されたものは上位に表示されます。
この違いから、「フォロー中」は自分主体のタイムライン、「おすすめ」はアルゴリズム主体のタイムラインと言えます。
例えば最新ニュース速報やリアルタイムの実況を追いたいときはフォロー中タブが向いています。
一方、自分の興味領域で人気の話題や、有益な発信をする新しいアカウントを知りたいときにはおすすめタブが便利です。
Xのデフォルトではアプリ起動時におすすめタブが表示される設定になっており、まずアルゴリズムがおすすめする投稿群が目に入るよう設計されています(ユーザー設定で変更可能)。
ビジネス目的で運用する際も、この2つの違いを理解しておくことが大切です。
自社アカウントの投稿をフォロワー以外にも広げたいなら、おすすめタブに載る=アルゴリズムに評価されることが重要になりますし、逆にフォロワーに確実に情報を届けたいならフォロー中に依存しすぎずエンゲージメントを高める工夫が必要になるでしょう。
アルゴリズムの評価指標|エンゲージメント・滞在時間・関心度
アルゴリズムが投稿を評価し、表示順序を決める際に重視する指標には主に次のようなものがあります。
- エンゲージメント(反応)指標: いいね・リポスト(リツイート)・リプライなど、ユーザーからその投稿へのアクションの量と質です。多くのユーザーから「いいね」や「リポスト」を集めている投稿は人気が高いと判断され、より表示されやすくなります。特にリプライ(返信)の数も重要です。単に静観されている投稿より、ユーザー同士で活発に会話が交わされている投稿の方が「注目度が高い」と見なされ、優先的に拡散されやすい傾向があります。総じて、ユーザーから多くの反応を引き出す投稿ほどアルゴリズム上有利になると言えます。エンゲージメント率(インプレッション数に占める反応数の割合)が高い投稿は評価が高く、おすすめにも載りやすくなります。
- 閲覧・滞在時間: 投稿に対してユーザーがどの程度長く留まって読んだか、リンク先まで開いたか、メディアを視聴したかといった滞在時間も重要な指標です。例えば2秒でスクロールを通過される投稿よりも、しっかりと全文を読まれたり画像・動画をじっくり見られた投稿の方が「ユーザーの関心を強く引いた」と評価されます。実際、2023年に公開されたアルゴリズムのコードでも「投稿を2分以上閲覧したユーザーが多いとスコア加点される」ことが明らかになっています。このため文章量が多く読み応えのあるツイートや、動画付きで再生時間の長いツイートは、有利に働きやすいのです。「ユーザーの時間を奪うコンテンツ」が伸びるという表現もありましたが、まさに他の投稿より長く注意を引きつけるツイートが評価される傾向にあります。
- ユーザーとの関心度・関連性: その投稿内容が各ユーザーの興味関心にどれほどマッチしているかという指標です。アルゴリズムは、各ユーザーごとに「興味のあるトピック」や「仲の良いユーザー関係」を把握しています。例えば普段からテクノロジー系の情報ばかり見ているユーザーには、テクノロジー関連の投稿が表示されやすく、スポーツに関する投稿は表示されにくくなります。また自分がよく交流している(相互にいいね・リプライしている)相手の投稿は、関係性が深いとみなされ優先表示されます。このようにユーザーごとの関心に合致する度合いもスコアリングされ、高いほどおすすめに載りやすくなるのです。企業アカウント運用では、自社のターゲット層(フォロワー層)の関心に沿った話題を提供し続けることで、この関連性スコアを高められます。
- 投稿の鮮度(新しさ): 投稿されてからの経過時間も考慮されます。一般にXでは新しい投稿ほど優先的に表示されやすく、時間の経った投稿は徐々に露出が下がります。特に話題性のある内容は投稿直後に一気に反応が集まることで短時間で広く拡散されます。アルゴリズム上も、投稿後数時間以内に獲得した反応はそれ以降より高く評価される仕組みになっており、初動が重要です。具体的には投稿後6時間以内に得たいいねやリツイートは、それ以降に得た同じ反応よりもアルゴリズムスコアへの寄与度が大きいことがわかっています。したがって投稿のタイミングや初期拡散を意識することは、アルゴリズム攻略上欠かせません。
以上のように、Xのアルゴリズムはユーザーからの反応量と質、閲読状況、そして内容の関連度や投稿後の時間経過など複合的な指標に基づいて各ツイートの表示可否や順位を決定しています。
それらを総合して評価スコアが算出され、高スコアな投稿ほど多くの人のタイムラインに現れるのです。
アルゴリズムを味方につけるには、これら評価指標で高得点を取れるような投稿を心がける必要があります。
アルゴリズムが重視する要素
アルゴリズムに評価されやすい投稿にはどんな共通点があるのでしょうか。
ここではアルゴリズムが特に重視する4つの要素を中心に解説します。
これらを理解し対策することで、投稿が「おすすめ」に載る確率を高め、より多くのユーザーにリーチすることが可能になります。
エンゲージメント率(いいね・リポスト・リプライ)の重要性
アルゴリズムは投稿のエンゲージメント率を非常に重視します。
エンゲージメント率とは、その投稿が見られた回数(インプレッション)に対して、いいね・リポスト・リプライなどの反応がどの程度あったかを示す割合です。
単純な反応数だけでなくインプレッションあたりの反応率を見ることで、「どれだけその投稿が人々の興味を引いたか」が測られます。
特にリプライ(返信)の存在感は大きいです。Xのアルゴリズムは「ユーザー同士の交流が活発な投稿」を高く評価する傾向があり、リプライが多く付いているツイートは「会話が生まれている=注目度が高い」と見なされます。
リプライは単なるリアクション以上に、投稿者とユーザー間、ユーザー同士のコミュニケーションを示すものです。
実際、アルゴリズムの内部スコアではリプライ1件が「いいね」数十件分に相当する価値を持つとも言われ、非常に重みづけされています(公開コードの解析によれば、いいねのスコアを1とするとリプライはおよそ27倍のスコアが与えられていました)。
また投稿者がリプライに対してさらに返信を返すと、そのやり取りの双方のアカウント評価が上がるというデータもあります。
つまり双方向のコミュニケーションが活発なほどアルゴリズム上有利になるのです。
いいねやリポスト(リツイート、引用リツイート)ももちろん重要なシグナルです。
特にリポストは「この投稿を他の人にも広めたい」という意思表示であり、人気度を示します。多くのユーザーからリポストされている投稿はより一層おすすめ表示されやすくなります。
いいねの数も基本的な人気指標ですが、アルゴリズムはいいね単体よりもリプライやリポストなど能動的なアクションを高く評価する傾向があります。
いいねはワンクリックの軽い反応であるのに対し、リプライは時間をかけてコメントする積極的関与、リポストは自分のフォロワーにも共有する影響力行使だからです。
そのため、エンゲージメント率を高める際は「いいねを増やす」だけでなくリプライや引用ツイートを促す工夫が有効です。
例えば投稿文に質問を入れて回答を募ったり、意見を聞く形にするとリプライが付きやすくなります。
また単に情報発信するだけでなく「この話題について皆さんはどう思いますか?」と投げかけるだけでも、反応率は上がるでしょう。質の高いエンゲージメントを増やすことがアルゴリズム攻略の鍵なのです。
ポストの初速と拡散力|バズに繋がる仕組み
投稿後の初動(初速)もアルゴリズム上極めて重要な要素です。
ツイートを公開してから最初の1〜2時間でどれだけ反応を集められるかが、その投稿が「バズる(急激に拡散する)」かどうかを左右します。
アルゴリズムは投稿が新鮮なうちに高エンゲージメントを示すと「価値ある旬の情報」と判断し、さらに露出を増やす好循環が生まれます。
特に投稿後6時間以内に得られたエンゲージメントは高く評価されます。
例えば投稿直後にフォロワーが一斉にいいね・リポストしてくれた場合、その勢いでフォロワー外にもおすすめ表示され、さらに反応が付く…という連鎖が起きます。
逆に言えば、6時間経ってからどれだけ反応が増えても、初期に反応ゼロだった投稿より評価が伸びにくいのです。
同じ100件のいいねでも、最初の1時間で付いた100件と2日かけて付いた100件では前者の方が遥かにアルゴリズム上有利ということです。
この仕組み上、投稿の拡散力を高めるには初動を意識した運用が不可欠です。具体的なポイントとしては次のようなものがあります。
- 投稿のタイミング: フォロワーがアクティブにXを見ている時間帯を狙ってツイートすることで、すぐに反応が付きやすくなります。一般的に平日であれば朝の通勤時間帯(7〜9時)や昼休み(12〜13時)、夜のリラックスタイム(20〜22時)などは多くのユーザーがオンラインになる傾向があります。自社アカウントのフォロワー層の生活パターンに合わせ、投稿時間を調整しましょう。Xアナリティクスの「オーディエンス」データでフォロワーのアクティブな時間帯を確認し、それに合わせてスケジューリングすると効果的です。
- 投稿頻度と継続性: 初速を上げるにはフォロワーとの日頃の関係構築も大切です。普段から定期的に投稿していればフォロワーのタイムラインに露出する機会が増え、エンゲージメントの習慣もつきます。逆に長期間投稿がないアカウントだと、たまに投稿してもフォロワーに気づかれにくかったり興味を持たれにくくなります。一般的な企業アカウントでは少なくとも毎日1回程度の投稿を継続するのが望ましいです。もちろん質も大事ですが、最低限の頻度を維持して「常に誰かのタイムラインに自社の投稿が流れている状態」を作りましょう。
- トレンドの活用: 初速を稼ぐテクニックとして、トレンド入りしている話題や旬のハッシュタグにタイミングよく乗る方法もあります。その時多くのユーザーが注目しているキーワードを投稿に盛り込むことで、エゴサーチ的に見つけられてエンゲージメントが付きやすくなります。ただし無関係なトレンド乱用は逆効果ですので、あくまで自社に関連する話題でタイミングが合うものを選びましょう。
以上のような工夫で投稿直後の反応を最大化できれば、アルゴリズムがそれを検知してさらに露出を増やし、結果的にバズにつながる可能性が高まります。
バズは偶然ではなく初動設計の産物とも言えるのです。
ネガティブ評価(通報・ミュート・ブロック)の影響
アルゴリズムはユーザーからのネガティブな反応にも敏感に反応します。
具体的には、「この投稿を見たくない」と思われる行為、すなわちミュート(投稿主をミュート)やブロック、投稿の報告といったアクションがそれに当たります。
これらが多く発生した投稿やアカウントは、アルゴリズム上評価が下がり、タイムライン上で他のユーザーに表示されにくくなります。
特に深刻なのは「ポストの報告(スパム報告・不適切報告)」です。
これは運営側にも通知されるため、アルゴリズム上も大幅な減点対象となります。
またブロックやミュートも、「その投稿者のコンテンツは見たくない」というユーザーの明確な意思表示であり、一定数以上積み重なると投稿の露出が制限される可能性が高まります。
公開されたアルゴリズムの情報によれば、ブロックやミュート1件あたりのマイナス影響度は、いいね数百件分に匹敵するほど大きいという分析もあります。それだけ「嫌がられている」サインをアルゴリズムは重く見ているということです。
したがって、企業アカウント運用においてもネガティブな反応を招かない配慮が必要です。
具体的には、攻撃的・挑発的な投稿や不快感を与える表現は避けること、広告色が強すぎて敬遠されないよう工夫することが挙げられます。
また近年のアップデートでは「より情報的で楽しいXを目指すためネガティブな情報を減らす」アルゴリズム変更が行われており(2025年1月のマスク氏の発言)、ポジティブで建設的な内容が優遇される傾向が強まっています。
誹謗中傷や愚痴ばかりのアカウントはユーザーから敬遠されるだけでなく、アルゴリズムからも評価を下げられるリスクが高いのです。
なお、ネガティブ評価の対策としてユーザーからのフィードバックを真摯に受け止める姿勢も重要です。
万一クレーム的な返信や引用リツイートが付いた場合も感情的に反論せず、冷静かつ丁寧に対応することで事態の沈静化を図りましょう。
炎上してしまうと一時的にエンゲージメントが増えるように見えても、長期的にはアルゴリズム上マイナスに働きます(表面的な炎上エンゲージメントより真の価値あるコンテンツを評価する方向に変化しています)。
「無用な敵を作らない」運用が、アルゴリズム的にも賢明と言えます。
メディア要素(画像・動画・スペース・リンク)の扱われ方
投稿に含まれるメディア要素(画像や動画、音声スペースへの参加告知、そして外部リンク)はアルゴリズム上さまざまな影響を及ぼします。
まず画像や動画については、総じてポジティブな効果があります。
テキストだけの投稿よりも視覚的なコンテンツを伴う投稿の方がユーザーの目を引きやすく、結果として閲覧時間が伸びエンゲージメントも増える傾向があります。
アルゴリズムもこの点を考慮しており、「画像や図解付きのポスト、動画付きのポストの方が伸びやすい」のはユーザーの滞在時間が上がりやすいためだと説明されています。
実際、動画コンテンツは優先的に表示される傾向があるとの分析もあり、Xを伸ばしたいなら積極的に動画を活用することがおすすめです。
Elon Musk氏自身も動画機能の強化に言及しており、長尺動画の投稿やクリエイターによる動画配信をX内で完結させようという動きがあります。
これはユーザーの滞在時間を増やし他プラットフォームへの離脱を防ぐ狙いがあるため、アルゴリズムも動画コンテンツを歓迎していると言えるでしょう。
次にスペース(音声ライブ配信)についてです。
Twitter時代から導入されたライブ音声機能である「スペース」も、Xプラットフォーム内で重視されるメディアの一つです。
フォローしているユーザーがスペースを開始するとアプリ上部に通知が出たり、タイムライン上部に参加中のスペース情報が表示された経験があるかもしれません。
これはアルゴリズムがスペースというリアルタイムコンテンツをユーザーに積極的に知らせる動きをしている証拠です。
特にElon Musk氏が参画後、Xは「オールインワンのプラットフォーム」を目指しており、ライブ音声や将来的な動画ストリーミングなどリアルタイム性の高いコンテンツを重視しています。
スペースで多くの聴衆を集めれば、その開催者のアカウントは一種の「人気コンテンツ提供者」として評価され、フォロワー獲得や影響力向上につながります。
またスペースでの会話内容も将来的にはAIによってテキスト解析され、興味分野の把握に使われる可能性もあります。
まだ直接的に通常投稿のアルゴリズムランキングに影響するか明言されてはいませんが、少なくともX上でスペース等の新機能を活用すること自体がプラットフォーム内評価を高める効果は期待できます。
一方で外部リンクの扱いには注意が必要です。
Xのアルゴリズムはプラットフォームからユーザーが離脱する行為を嫌う傾向があります。
そのため、外部サイトへのURLを貼り付けた投稿はエンゲージメントが同等ならリンクなしの投稿よりも表示優先度が下がる、と公式に明言されています。
2024年11月にはElon Musk氏が「リンク付き投稿は表示優先度を下げる」と公表し、多くのマーケターに衝撃を与えました。
これは裏を返せば、「ユーザーを他サイトに逃がす投稿はX上であまり歓迎されない」ということです。実際、リンク付きツイートはいいね等の反応も得られにくい傾向がデータ上指摘されています。
ではビジネス用途でやむを得ず自社サイト等へのリンクを投稿したい場合はどうすればよいでしょうか。
効果的な対策として推奨されているのが、本題の投稿ではリンクを貼らず十分な内容説明を書き、追伸的に自分のリプライでリンクを提示する方法です。
こうすることで、メインの投稿自体はリンクなしとしてアルゴリズム減点を回避しつつ、興味を持った人にはリプライのリンクから詳細へ誘導できます。
またリンク先ページのプレビューカードが自動展開されないため、投稿自体の見た目もすっきりします。
このテクニックは多くのSNS運用担当者が実践しており、外部リンクの利便性とアルゴリズム対応を両立する有効策と言えるでしょう。
まとめると、画像・動画といったリッチメディアは積極活用し、外部リンクはできるだけメイン投稿に含めないか工夫することが、アルゴリズムに好まれる投稿作りのポイントです。
X内でユーザーの閲覧体験が完結するよう心がけ、必要に応じてスペース等の新機能も取り入れることで、アルゴリズム上の評価も高まりやすくなります。
アルゴリズムに好まれる投稿の特徴
アルゴリズムに評価されやすい投稿の特徴を踏まえつつ、具体的にどのような投稿が効果的かを見ていきましょう。
タイミングや頻度、テキストやハッシュタグの工夫、そしてコミュニケーション性の高い投稿スタイルなど、いくつかの観点から「アルゴリズムに好まれる投稿」を解説します。
タイミングと頻度|いつ投稿すべきか
投稿のタイミングは前述したように非常に重要です。
一般論としてはフォロワーがオンラインになりやすい時間帯—平日なら朝の通勤・通学時間や昼休み、夜のゴールデンタイム—を狙うと初速のエンゲージメントが得られやすくなります。
特に企業・ビジネスアカウントの場合、フォロワーも日中仕事をしている社会人というケースが多いため、朝8~9時台やお昼12時台~13時台、そして夜20~22時台あたりが一つの目安になるでしょう(業種やターゲットによって異なりますが)。
例えばBtoB企業なら朝出社前やお昼休み、BtoC商品なら夜リラックスタイムにSNSを見る人が多い、といった具合です。
しかし最適な時間帯はフォロワー属性によっても異なります。
自分のフォロワーがいつアクティブかを把握するには、Xアナリティクスの「オーディエンス」タブで時間帯別のアクティブユーザー数を確認すると良いでしょう。
このデータを参考に、例えば「フォロワー層は夜型が多いから21時台に投稿しよう」など戦略立てが可能です。
また曜日によっても傾向があります。平日は朝昼が強くても、土日は夜がメインになる場合もあります。
いずれにせよ、フォロワーが最も見てくれるタイミングを狙って投稿することで、アルゴリズムに乗るための初期反応を集めやすくなります。
投稿頻度については、アルゴリズム上「多すぎても少なすぎても良くない」とされています。
長期間まったく投稿しないとアカウントの存在感が薄れますし、逆に短時間に大量の投稿(例えば1時間に10件以上など)を連発するとスパム的と見なされフォロワーにも敬遠されがちです。
理想的には毎日1〜3件程度のポストを安定して行うのがおすすめです。
最低でも週数回以上はコンスタントに投稿し、「このアカウントは常に最新情報を発信している」という印象を与えると良いでしょう。
頻度を上げる際はネタの質が落ちない範囲で調整し、一度にまとめて投稿するのではなく時間帯を分散して露出機会を増やす工夫も有効です。
アルゴリズムはユーザーのログイン頻度や投稿頻度自体も見ている可能性があります。
実際、毎日アクティブなユーザーはタイムライン上でも優遇されやすいとも言われます。
したがって企業で複数人で運用している場合は投稿当番を決めてでも1日1ツイートは欠かさないようにし、休眠期間を作らないようにしましょう。
継続的で規則正しい発信が、フォロワーとのエンゲージメント習慣を育て、アルゴリズムからの評価も安定させます。
テキスト・ハッシュタグ・リンクの最適化
投稿テキストの書き方もアルゴリズム攻略には重要です。
まず心掛けたいのは、テキストの冒頭部分で読者の興味を引くことです。
タイムラインでは限られた文字数(全文の最初の一部)しか表示されないため、冒頭で惹きつけられないと「続きを読む」をタップしてもらえません。
仮に長文ツイートを用意していても、最初の一文が単調だとスルーされ閲覧時間が稼げず、結果的にエンゲージメントも低くなります。
そこで、投稿の最初に質問形で始めてみたり、驚きのデータや結論を端的に述べたりして、ユーザーの関心をグッと掴む構成にしましょう。
「え、それ本当?」「続きを知りたい」と思わせる書き出しは、最後まで読んでもらう(=滞在時間を伸ばす)上で有効です。
ハッシュタグの活用については、使い方次第でメリット・デメリットがあります。
メリットとしては、関連するハッシュタグを付けることで検索やトレンド経由で新たなユーザーに発見されやすくなる点です。
特に業界固有のコミュニティタグや、イベント公式ハッシュタグなどは積極的に利用すると良いでしょう。
また、前述の通りTwitterのトレンド入りしているキーワードをハッシュタグとして織り交ぜることで一時的な拡散力を高める手法もあります。
一方でハッシュタグの乱用は逆効果になり得ます。
過剰に多くのハッシュタグを付けるとスパムっぽく見えるだけでなく、アルゴリズム上も敬遠される傾向があります。
目安として1ツイートに付けるハッシュタグは多くても2つ程度に留め、内容と直接関係のないタグは付けないようにしましょう。
FacebookやInstagramのように大量のハッシュタグを羅列する文化はXにはありません。
むしろ近年はアルゴリズムの高度化により、ユーザーはハッシュタグがなくても関連話題の投稿を流れてくるケースが増えています。
「ハッシュタグ離れ」という言葉もあるように、必須のもの以外は無理に付けずテキストの自然さを優先する方が良いでしょう。
外部リンクの扱いについては前項でも触れましたが、再度ポイントをまとめます。
Xでは外部リンク付き投稿の表示優先度が下がる公式発表があり、実際リンクを貼るとエンゲージメントが落ちる傾向があります。
そのため、可能な限りメインの投稿にはリンクを含めず、詳細情報や誘導先URLはスレッドの2番目以降(自分の返信)に記載する方法が推奨されます。
例えば新商品の紹介ツイートなら、1件目の投稿で魅力や概要をしっかり伝え、2件目のリプライで「詳細はこちら」と公式サイトのリンクを貼るイメージです。
こうすれば1件目のツイート単体ではリンク無しとして評価され、内容が興味深ければアルゴリズムに乗るチャンスが増します。
リンク先に飛んでもらうハードルはやや上がりますが、その分投稿自体のリーチは確保できるため結果的に流入数も向上することが多いです。
またリンク以外にも、メンション(@ユーザー名)の使い方も注意が必要です。
他のユーザーへの言及も多用しすぎるとスパム判定される可能性があります。
キャンペーン等で多数のユーザーをメンションする場合は、小分けにするか一部伏せ字にするなど工夫した方が無難です。
アルゴリズムは不自然な大量メンションを「迷惑行為」とみなす可能性があるからです。
要するに、テキストは簡潔かつフック重視、ハッシュタグは厳選して適切に、リンクは貼りすぎない…これが投稿コンテンツ最適化の基本です。
読み手視点に立って「思わず反応したくなる/最後まで読みたくなる」文章を心掛け、不要な装飾やリンクは控えることで、結果的にアルゴリズムの評価も上がっていくでしょう。
コミュニケーション性の高い投稿(リプライ・引用)の効果
Xのアルゴリズムはユーザー間のコミュニケーションを非常に重視しています。
単方向に情報発信するだけでなく、双方向のやり取りが活発なアカウントや投稿は、タイムライン上で優遇される傾向があります。
そこで重要になるのがリプライや引用リポスト(引用ツイート)といった形でのコミュニケーション性の高い投稿です。
まずリプライについて。
自分の投稿にユーザーからリプライ(返信)がたくさん付くと、その投稿はアルゴリズム上「注目度が高い」とみなされ、おすすめ表示される確率が高まります。
さらに、リプライは「した側」と「された側」両方のフォロワーのタイムラインに表示される可能性があるため、単一のいいねよりも投稿の拡散範囲を広げる効果があります。
つまりフォロワー以外にも会話相手のフォロワー層にコンテンツが露出するわけです。
例えばインフルエンサー的なユーザーがあなたの投稿にリプライしてくれれば、その人のフォロワー多数にもあなたの投稿が届き、新規フォロワー獲得につながるかもしれません。
逆に自分から人気アカウントの投稿へ質の高いリプライを送ることで、その投稿を見た第三者の目に留まりフォローされる、といった効果も期待できます。
リプライは新たな露出のきっかけにもなるわけです。
次に引用リポスト(旧称:引用リツイート)について。
こちらは他人の投稿を自分のコメント付きで共有する機能です。
引用リポストされた場合、元の投稿者には通知が行くため認知されるチャンスになるほか、引用した人のフォロワーには元ツイートとコメントがセットで表示されます。
アルゴリズム的には通常のリポストと同様「他者にシェアされた」という点でポジティブに評価されますし、コメントが付く分リプライにも近い効果を持ちます。
自分が引用される立場になるのがベストですが、それだけでなく自分から有益な他者の投稿を引用紹介するのも有効な戦術です。
例えば業界ニュースに対して見解を添えて引用ツイートすれば、情報キュレーターとしての評価が上がり、元投稿者やそのフォロワーとの接点が生まれます。
結果として交流関係が広がり、自分の投稿も将来的に相手のタイムラインに載りやすくなるかもしれません。
いずれにせよ、積極的にコミュニケーションを取る姿勢がアルゴリズム攻略には重要です。
自分の投稿へのリプライにはできるだけ返事をし、会話を継続させましょう。
返信を返すことでさらにエンゲージメントが増え、その投稿やアカウントの評価も上がります。
またフォロワーからの質問に答えたり感謝のコメントを述べたりすることで、ユーザーとの信頼関係も深まります。
さらに、可能であれば業界内の話題に積極的に参加することも有効です。
例えば同業種の人気アカウントが投げかけた質問に自社の見解をリプライする、流行中のハッシュタグ企画に便乗して自社のネタを投稿する、といった形で交流を図ります。
他アカウントとのコラボ投稿(相互にリプライし合うような企画)なども、双方のフォロワーが交差する良い機会になります。
このように、Xでは「コミュニケーションした者勝ち」の側面があります。
アルゴリズムもそれを理解しており、日頃からDMやリプライで交流が深いユーザー同士の投稿は優先表示される仕組みです。
ですから企業アカウントであっても一方通行の告知ばかりではなく、ユーザーとの会話やコミュニティ作りに力を入れることが肝要です。
結果的にそれがアルゴリズムへの高評価にもつながり、投稿の露出増→さらに新しいフォロワー獲得…という好循環を生み出すでしょう。
アルゴリズムとアカウント運用戦略
アルゴリズムの仕組みを理解したうえで、日々のアカウント運用にどう活かすかを考えてみましょう。
ただ闇雲に投稿するよりも、アルゴリズムに沿った戦略を持って運用した方が効率よく成果を出せます。
以下では、プロフィール最適化、フォロワー属性の重要性、そしてアナリティクス活用という3つの観点から運用戦略を解説します。
プロフィール最適化で表示優位を得る方法
意外に見落とされがちですが、プロフィールの最適化もアルゴリズム攻略の一助になります。
厳密に言えばプロフィール情報そのものがタイムラインのアルゴリズムランキングに直接作用することはありません。
しかし、プロフィールを工夫することでフォロワーの増加やエンゲージメント改善につながり、結果的にアルゴリズム評価が高まる効果が期待できます。
まず、ユーザーがあなたのアカウントをフォローするかどうか判断する際、必ずプロフィール(自己紹介文やプロフィール画像、固定ツイートなど)に目を通します。
興味を引かれるプロフィールであればフォローしてもらえ、そうでなければスルーされてしまいます。
一般に、訪問者がプロフィールを見て「フォローしようかな?」と判断を下すまでの時間はほんの数秒(6秒程度)と言われています。
その短時間で「このアカウントをフォローするとこんな情報が得られる」という魅力を伝える必要があります。
具体的なポイントとしては:
- アイコン画像・ヘッダー画像: 視覚的に信頼感や興味を引くものにします。企業アカウントならロゴやキャラクター、人物写真なら明るくはっきりと分かるものを使いましょう。
アイコンやヘッダーにお悩みの方は以下の記事も読んでみてください。こちらの記事で、アイコンやヘッダーに関する説明から、伸ばすための秘訣まで解説しています。
-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-18-300x169.png)
- プロフィール文: 箇条書きや絵文字を適度に使って読みやすくまとめます。自社の事業内容や発信トピック、実績(フォロワー◯万人、受賞歴など)がひと目で伝わると良いでしょう。「このアカウントをフォローすると○○な情報が手に入ります」とフォロワーのメリットを明記するのも有効です。企業・店舗アカウントの場合は所在地や営業時間、公式サイトURLなど信頼性を担保する情報もしっかり記載します。
- プロフィール内キーワード: 自社業界や専門分野のキーワードを盛り込むことで、検索やおすすめユーザーに表示される可能性が上がります。例えば「SNSマーケ担当」「キャンペーン情報発信中」など、ひと目で何者かわかるワードを入れましょう。ただし過剰なタグや謳い文句の羅列は逆効果ですので簡潔に。
- 固定ツイート: プロフィール訪問時に最上部に表示される固定ツイートも活用しましょう。代表的な実績紹介や人気ツイートを固定しておけば、新規訪問者にアピールできます。キャンペーン告知など期間限定の案内にも便利です。
こうしたプロフィール最適化により、新規フォロワー獲得率が上がれば、フォロワー数増加→エンゲージメント母数増加→アルゴリズム評価アップという好循環が生まれます。
また、プロフィールを充実させ信頼感を高めておくことはエンゲージメント率向上にも寄与します。
人はプロフィールを見て「この人なら反応しても大丈夫」と感じると、いいねやリプライをしやすくなる心理があります。
逆に素性がよくわからないアカウントだとスルーされがちです。特に企業公式であればなおさら、公式HPへのリンクや認証バッジ取得(後述のX Premium)などで「公式感」を出すことが重要です。
さらに、プロフィールや発信内容が明確だとアルゴリズム上のアカウントカテゴライズにも有利です。
Xのアルゴリズムはユーザーを興味関心の近いコミュニティ(クラスタ)に分類していると言われます。
プロフィールに含まれるキーワードや日頃の投稿内容から「このアカウントは○○領域」と判断されるため、ブレのないテーマ設定で発信した方が特定分野のクラスタ内でおすすめに載りやすくなります。
例えばプロフィールやツイートで一貫して「デジタルマーケティング」という言葉が出てくるアカウントは、そのトピックに興味のあるユーザーのタイムラインに表示されやすいでしょう。
総じて、プロフィールはアカウントの顔です。第一印象を良くし、フォロー→エンゲージメントという流れを生みやすくする工夫を凝らすことで、間接的にアルゴリズム上の有利なポジションを築くことができます。
フォロワー属性とアルゴリズムの相性
アルゴリズムに評価されるためには、フォロワーの質や属性にも目を向ける必要があります。
極端に言えば、興味の薄いフォロワー1万人より、関心度の高いフォロワー1000人の方がアルゴリズム上は有利に働くケースもあります。それはなぜでしょうか。
まず、アルゴリズムが投稿を他のユーザーにおすすめ表示する際、その投稿への初期反応を左右するのは主にフォロワーです。
フォロワーがすぐに反応してくれれば初速が付きおすすめに乗りやすくなり、フォロワーが無反応だとおすすめに広がらないまま埋もれてしまう可能性があります。
したがってフォロワーの興味分野が自分の発信内容とマッチしていることが重要なのです。
例えばフォロワーの大半が学生でエンタメ目的なのに自社がBtoB向け堅め情報ばかり発信していては、フォロワーは反応してくれないでしょう。
逆にフォロワーが自社業界の関係者や興味層で固まっていれば、投稿ごとに一定のエンゲージメントが見込め、アルゴリズムにも乗せやすくなります。
次に、フォロワー自体のアクティブ度も重要です。仮に1万人フォロワーがいても、半分以上が休眠アカウントやBOTでは意味がありません。
アルゴリズムから見たアカウント評価の一つに「フォロワー数とフォロー数の比率」があります。
一般にフォロワー数が多くフォロー数が少ない(=影響力がある)アカウントは優遇され、逆にフォロー数ばかり多くフォロワーが少ない(=フォロバ狙いでばら撒いているような)アカウントは評価が低くなります。
これは不健全なフォロワー集めを牽制する目的があります。
従って、フォロー・フォロワー比が極端に悪化しないよう注意が必要です。
具体的には自分がフォローしている数よりフォロワーの方が多い状態が望ましいです。
仮に新規アカウント立ち上げ時にフォロー>フォロワーとなってしまっても、軌道に乗ったら整理し、フォロー数を適切に抑えていくと良いでしょう。
また、フォロワーの中身がスパム的なものばかりだとアルゴリズム評価に悪影響を及ぼす可能性もあります。
以前、フォロワー購入などで水増ししたアカウントが軒並みエンゲージメント率低下とともに露出も減っていく事例がありました。
アルゴリズムはフォロワー数そのものよりもフォロワーとの相互作用を重視します。
仮にフォロワー1万人でも普段反応するのは数十人では、エンゲージメント率は0.1%以下となり評価は高まりません。
むしろフォロワー500人でもそのうち50人が常に反応してくれるならエンゲージメント率10%でアルゴリズム上は健全なコミュニティとして評価されるでしょう。
以上を踏まえると、「質の高いフォロワー」を地道に増やすことが最良の戦略となります。
質の高いフォロワーとは、あなたの発信内容に関心を持ち、自発的にいいねやリプライを送ってくれるフォロワーです。
そういうフォロワーが増えるよう、ターゲットに響く有益な情報を提供し続けましょう。
またフォロワー属性を把握するために、Xアナリティクスの「オーディエンス」データで年代・性別・興味関心などを分析してみてください。
自社の想定ターゲットとずれているようであれば、発信内容やハッシュタグ選定を見直して誘導していく必要があります。
最後に補足ですが、X Premium(旧Twitter Blue)の導入以降、認証済みフォロワーの比率も一部で話題になりました。
認証済みユーザー(青バッジ所持者)はアルゴリズム上優遇されるため、そういったユーザーにフォローされること自体が多少プラスになる可能性があります。
ただこれは直接的なものというより、そのような影響力者にフォローされる=良質なアカウントであるという間接的な評価でしょう。
あまり意識しすぎる必要はありませんが、一流の人にフォローされるアカウントを目指すくらいの意識で品質を高めていくと良いでしょう。
アナリティクスを用いたアルゴリズム対策の実践
アルゴリズム攻略の施策を考える上で、Xアナリティクス(Twitter Analytics)の活用は欠かせません。
アナリティクスは自分のアカウントの投稿に関する様々なデータを閲覧できる公式ツールで、各ツイートのインプレッション数やエンゲージメント数・率、フォロワー増減、オーディエンス属性などを把握できます。
これらのデータを分析することで、「どのような投稿がアルゴリズムに好まれているか」「どんな内容だと反応が良いか」を自社アカウント固有の傾向として掴むことが可能です。
具体的なアナリティクス活用方法をいくつか紹介します。
- エンゲージメント率の高い投稿を分析: 過去数ヶ月のツイートを振り返り、特にエンゲージメント率(いいね・リツイート・リプライなど反応数をインプレッションで割った値)の高かった投稿をピックアップします。それらに共通する要素は何かを考えましょう。例えば「質問形式の投稿は毎回反応が多い」「製品の豆知識を載せた投稿は保存(ブックマーク)が多かった」等です。アナリティクスではブックマーク数や共有(シェア)数も確認できますが、これらは「後で見返したい」「他人にも共有したい」という有益な情報の指標です。ブックマークやシェアが多い投稿はアルゴリズム上も高評価されている可能性が高いので、似た切り口のコンテンツを増やすと良いでしょう。
- 伸びなかった投稿の原因を探る: 反対に、インプレッションが伸び悩んだ投稿も分析対象です。例えば「外部リンクを貼った投稿はやはり他より露出が少ない」「〇〇の宣伝ツイートはエンゲージメント率が極端に低い」などの傾向が見えるかもしれません。もしリンク貼付で伸びにくいのであれば先述のリンク回避策を講じる、宣伝色が強すぎるなら情報提供型に内容を改める、といった改善が考えられます。アルゴリズムは正直で、数字に現れる結果がすべてです。過去のデータから学び、PDCAを回すことが重要です。
- フォロワー増減要因の分析: アナリティクスでは日別のフォロワー増減も追えます。増加が多いタイミングでどんな投稿をしたか、逆にフォロー解除が多発した投稿は何だったかを見てみましょう。例えば特定の話題を連投したらフォロワーが減ったなら、その話題はフォロワーに不評だった可能性があります。逆に有益なスレッド投稿がバズって一気にフォロワー○百人増えたなら、そうしたコンテンツを定期化すると良いでしょう。
- オーディエンスデータの活用: フォロワーの属性(性別比や年代、興味関心分野、最も関心の高いトピックなど)もアナリティクスでチェックできます。ここで自社の狙い通りの層がフォローしているかを確認します。もし想定ターゲットと乖離している場合、発信内容を軌道修正しないとエンゲージメントが上がりません。例えば20代女性向けの商材なのにフォロワーは30代男性が多いとなれば、内容を見直す必要があるでしょう。このようにフォロワー分析による軌道修正もアルゴリズム対応では大切です。
以上の分析を踏まえたら、次はKPIの設定とモニタリングです。
例えば「今月はエンゲージメント率○%を目標」「インプレッション月間10万を目標」など具体的な数値目標を立て、アナリティクスで達成度を確認します。
目標に届かなければ原因を考えて来月に活かす、といったサイクルを繰り返すことで、着実にアカウントのパフォーマンスが向上していきます。
それは即ちアルゴリズム上の評価向上にもつながり、投稿がさらに伸びやすくなる好循環を生みます。
なお2024年後半以降、Xアナリティクスの仕様変更で一部ユーザーは利用に制限が出ているとの報告があります。
基本的にX Premium加入者は利用可能ですが、もし見れない場合は外部の分析ツール(X APIを使ったマーケティングツールなど)を検討すると良いでしょう。
データが見えなければ改善もできませんから、環境を整備して定量的な運用改善に取り組んでください。
まとめると、「分析なくしてアルゴリズム攻略なし」です。
勘や経験だけに頼らず、必ずデータで裏付けを取りながら運用戦略を練っていきましょう。それが最短で成果を上げる秘訣です。
2025年版|Twitter Xアルゴリズムの最新動向
2024年から2025年にかけて、X(旧Twitter)のアルゴリズムには大きな変更やトレンドの変化が見られました。
ここでは過去の変更点と現在の傾向、動画・スペース重視へのシフト、そしてAI導入によるおすすめ精度向上について、最新情報を整理します。
過去の変更点と現在の傾向
2023年3月にアルゴリズムの一部オープンソース化が行われ、以降ユーザーからのフィードバックを受けて細かな改善が繰り返されています。
公開コード解析により、Xのアルゴリズムが様々なスコアリング要素を持つことが明らかになりました。
例えば「X Premiumユーザーはブーストされる」「リプライに返信するとスコア大幅アップ」「ブロックやミュートでスコア激減」「新アカウントの外部リンクは避けられる」等、具体的なルールが存在していたのです。
この透明性向上により、運用者側も対策が立てやすくなりました。
2024年後半にはアルゴリズムの大幅改修が実施されています。
特に2024年12月にX社エンジニアリングチームが発表したアップデートでは、「ポストやユーザーに設定するパラメータを10倍に増やし、リアルタイム学習を5倍速化、計算量を3倍に拡大する」という大規模強化が行われました。
これによりユーザー行動への追随精度が上がり、より細かな嗜好まで反映されるアルゴリズムになったと言われます。
この変更の結果、それまでインプレッションを稼げていた投稿でも12月以降表示されにくくなる可能性がある、とも指摘されました。
逆に新アルゴリズムに適応した投稿であれば大幅なインプレッション増加も期待できるとのことで、運用者側には対応が求められました。
2025年1月にはイーロン・マスク氏が「より情報的で楽しいプラットフォーム」を目指し、ネガティブな情報を減点強化するアルゴリズム変更を示唆しました。
これは前述の通り、攻撃的・中傷的な投稿へのペナルティを強め、ユーザーが「見て後悔しない時間」を最大化する狙いがあります。
この頃からポジティブで建設的な内容を評価する傾向が一段と強まりました。「嫌われない運用」がより重要になったとも言えます。
現在(2025年)までの傾向をまとめると、「アクション重視・課金ユーザー優遇」の流れが一層強まったことが挙げられます。
多くの反応を集める人気アカウントや、X Premiumに加入しているアカウントが露出で有利になっています。
また、アルゴリズムの透明化やアップデートを経て「誰に表示されやすいのか」が明確になってきたため、運用者はそこに戦略的に乗る必要があります。
例えば前述のようにフォロー・フォロワー比の不健全なアカウントは表示されにくい、といったルールがある程度共有されたので、それを踏まえてフォロー整理する等の対策を取るわけです。
さらにハッシュタグの重要性低下も一部指摘されています。
かつてはトレンドに入れるほどハッシュタグが重宝されましたが、最近ではアルゴリズムが文脈理解をするため必ずしもタグがなくても関連投稿が表示されます。
そのため無理にタグだらけのツイートをするより、文章そのものの質で勝負する方がよいとの声もあります。
このあたりも「アルゴリズムの賢化」に伴う運用トレンドの変化と言えるでしょう。
まとめると、2025年現在のアルゴリズムは「ユーザーの興味に極限まで最適化され、かつ有益で前向きなコンテンツを優遇する」方向に進化してきたと言えます。
これを踏まえて運用者は、質の高いコンテンツ作りとユーザーフレンドリーな姿勢をより一層心がける必要があります。
動画・スペース重視のシフト
2025年のXプラットフォームにおいて顕著なのは、動画コンテンツへのシフトです。
Twitter時代にはテキストと画像主体だったタイムラインも、Xへのリブランディング後は動画投稿が増加し、アルゴリズムも動画を重視する傾向を見せています。
具体的には、X Premiumユーザーは長時間動画の投稿が可能になり、有料で動画コンテンツを配信する仕組み(サブスクライブ機能)も提供されました。
Elon Musk氏はクリエイターがYouTubeではなくX上で動画を投稿・マonetizeする未来図を描いており、動画視聴にユーザーを留めることでプラットフォームの価値を高めようとしています。
そのため、アルゴリズムも動画付き投稿を優遇してタイムライン上部に表示するケースが増えていると言われます。
実際、多くの企業アカウントでも動画(製品紹介やブランドストーリー動画など)を積極的に投稿する例が増えました。
またライブ音声機能「スペース」も引き続き注目されています。
Clubhouseに触発される形で導入されたTwitter Spacesですが、Xとなった現在も大型イベントの生中継や有名人のトークセッションなどに活用されています。
2025年には、大統領選関連の討論や企業カンファレンスの配信がスペース上で行われるなど、一部メディア的な役割も果たしています。
アルゴリズム面では、フォロー中のユーザーがスペースを開始するとプッシュ通知やタイムライン上部での告知が行われるため、通常投稿以上に目立つ形で認知されます。
これはXがスペースをエコシステムの重要要素と考えている証左でしょう。
スペースでの発言は記録に残らないためアルゴリズムスコアには直結しませんが、スペースでファンを獲得→フォロワー増加→通常投稿の伸びという好循環が狙えます。
全体としてXは「マルチメディア・プラットフォーム」への転換を進めています。
テキストだけでなく動画・音声・画像・投票(ポール)・コミュニティ機能など、多彩なフォーマットを提供し、ユーザーの目と耳を長時間引きつける狙いです。
当然アルゴリズムもそうした多様なコンテンツに対応し、例えば動画の再生維持率やスペース参加者数といった指標も内部的に考慮している可能性があります。
他SNSを見ても、動画プラットフォームは総じてエンゲージメントが高く、中毒性のある動画ほど評価される傾向があります。
Xも例外ではなく、「動画やライブでユーザーの時間を奪った者勝ち」な部分が増えていくでしょう。
実際、TikTok的な縦長動画をX上に投稿してバズらせているケースも散見されます。
企業のSNS担当者としては、こうした流れに乗り遅れないことが大切です。
文章や画像だけでなく、動画コンテンツやライブ配信企画を取り入れることでアルゴリズム上の恩恵を受けられるでしょう。
例えば製品の使い方動画、社員によるライブトーク、イベント現場からの生中継などをX上で行えば、従来リーチできなかった層にもリーチできるかもしれません。
2025年は動画重視へシフトする転換点であり、アルゴリズムもそれに追随しています。
「文字のTwitter」から「動画のX」へ…運用戦略もそれを意識したものにアップデートする必要があります。
AIによるおすすめ精度向上の背景
2025年に入り、Xのアルゴリズムには本格的にAI技術が統合され始めました。
その象徴的な出来事が2025年6月の「Grok AI」導入です。
GrokはElon Musk氏が立ち上げた新企業「xAI」が開発した大規模言語モデルで、チャットAIとしても公開され話題になりました。
その軽量版がXのレコメンデーションアルゴリズムに組み込まれ、「旧来のアルゴリズムからAIベースのアルゴリズムへ」大きく舵を切ったのです。
Grok AI統合の影響で、アルゴリズムの方針は「量から質へ」と大きく転換しました。
具体的には、以前はいいね数やフォロワー数といった量的指標が重視されがちでしたが、Grok導入後は投稿内容そのもののクオリティをAIが評価する仕組みに変化しています。
例えばポジティブで有益な投稿は従来以上に優遇され、逆にフォロワー数が少なくても質の高いコンテンツであれば上位表示される可能性が高まりました。
AIがテキストや画像の文脈をより深く理解し、「この投稿はユーザーに価値を提供しているか?」を判断できるようになったためです。
またGrok統合により、投稿の文脈や有益性をAIが判断するとも言われています。
単に炎上して表面的にエンゲージメントを稼ぐような投稿よりも、専門性が高い解説ツイートや心温まるストーリー投稿など「真の価値」があるコンテンツがきちんと評価される方向です。
これはTwitter時代に指摘されていた「炎上や極端な発言ほどバズりやすい」という負の側面を是正する試みとも取れます。
AIによってより精緻に投稿内容をスコアリングし、ユーザーが見て良かったと思える情報を上位に出そうという意図です。
Elon Musk氏は「後悔のないユーザー時間の最大化」をアルゴリズムのゴールに掲げています。
AIの活用はまさにその理念を技術的に支えるものです。
大量のデータを学習したAIは、個々のユーザーの趣味嗜好はもちろん、人間では気づけない投稿間の関連性や品質まで考慮できます。
その結果、おすすめフィードの満足度向上が期待されています。実際、「最近のおすすめは自分好みのものが増えた」「無駄なノイズ投稿が減った」というユーザーの声も一部では聞かれます。
もっとも現時点では過渡期であり、「AI導入後に特定の話題ばかり出るようになった」「偏りが強まった」との声もあります。
アルゴリズムのチューニングは続いている段階でしょう。
運用者として注目すべきは、AI時代のアルゴリズムでは小手先のテクニックより本質的な質が重要になるという点です。
例えば無意味にキーワードを詰め込むようなSEO的手法は、AIには見抜かれる可能性があります。
それよりもユーザーにとって本当に役立つ内容か、独自性や誠実さがあるかといった部分が問われます。
Grok AIは大量のデータから「良質な投稿」のパターンを学習しているはずなので、今後は質の低い量産ツイートは淘汰され、各投稿の価値勝負になると予想されます。
背景としては、他プラットフォームでもAIレコメンドが進んでいることがあります。
TikTokやInstagramの高度な推薦システムと競う上で、XもAI活用は必須でした。
Musk氏のxAIプロジェクトはその布石であり、2025年はその成果がX本体に現れた年と言えるでしょう。
今後もアルゴリズム改良のたびにAI色は濃くなっていくはずです。
要するに、「AIに評価される投稿とは何か」を意識する時代が来たということです。
人が見てもAIが見ても有益で面白いコンテンツ追求することが、これからのアルゴリズム攻略の本道になるでしょう。
奇をてらったり水増ししたフォロワーでバズ狙いといった手法は通用しにくくなっています。マーケ担当者としては正攻法で勝負する腹積もりで、コンテンツ力とコミュニケーション力を磨いていく必要があります。
よくある質問Q&A|アルゴリズムと運用の疑問
最後に、Twitter(X)のアルゴリズムや運用に関してよくある質問をQ&A形式でまとめます。企業やマーケ担当者の方が抱きがちな疑問にお答えします。
なぜ自分の投稿が伸びないのか?
- 投稿が伸びません!なぜですか!?
-
投稿が伸び悩む原因は様々ですが、アルゴリズムの観点から主な理由をいくつか考えてみましょう。
・エンゲージメント不足: 投稿内容がフォロワーの興味とマッチしていなかったり、反応を促す工夫が足りないと初動のいいね・リポストが付きません。初期反応が少ない投稿はアルゴリズム上高く評価されず、結果としてタイムライン露出も増えない悪循環になります。質問を投げかける、話題性のあるテーマを選ぶなど、まずはフォロワーから反応を引き出す工夫が必要です。・タイミングの問題: 投稿する時間帯によってはフォロワーがあまり見ておらず埋もれてしまうことがあります。例えば深夜や早朝に投稿すると反応が得づらく、そのままタイムライン下部に沈んでしまいます。自分のフォロワーがアクティブな時間帯を狙って投稿することで初速が付き、伸びやすくなります。
・コンテンツの質・フック不足: 投稿の内容自体がユーザーにとって有益でなかったり、冒頭の文言が惹きつけない場合もスルーされがちです。Twitter上では大量の情報が流れるため、読み手の注意を引くキャッチコピーや目新しい情報提供が不可欠です。もし投稿が伸びないときは、内容そのものを再点検し、より価値のある情報や魅力的な切り口に改善しましょう。
・メディア要素の欠如: テキストのみの投稿より、画像や動画付きの投稿の方が目に留まりやすく、エンゲージメントも高まる傾向があります。もし文字だけの投稿ばかりで伸びないなら、一度関連する写真や短い動画クリップを添えて投稿してみてください。視覚情報があるだけで反応率が上がり、アルゴリズム評価も向上します。
外部リンクの貼りすぎ: 毎回投稿に自社サイトやYouTubeなど外部リンクを貼っていると、どうしてもインプレッションが伸びにくくなります。リンク先に誘導したい気持ちは分かりますが、まずはX上で投稿自体を読んでもらわなければ始まりません。リンクは必要最低限に留め、紹介文で興味を引いてから自分のリプライに詳細リンクを載せる方法に切り替えてみましょう。
・フォロワーとのズレ: 投稿内容が現在のフォロワー層の関心とかけ離れている場合も伸びません。例えばフォロワーはマーケティング目当てなのに急に日常の雑談ばかり投稿しても反応は得にくいでしょう。オーディエンス分析を行い、フォロワーが求めている情報に沿った発信を心がけてください。
以上のような点をチェックし、必要に応じて改善することで徐々に投稿の伸びが良くなるはずです。特にエンゲージメント初動とコンテンツの質は伸びる・伸びないを分ける最重要ポイントです。アルゴリズムに文句を言う前に、まずは自分の投稿にこれらの改善余地がないか見直してみましょう。
フォロー・フォロワー比は関係ある?
- FF比が大切っていう話を先日聞いたのですが、正しいですか?
-
はい、フォロー・フォロワー比(FF比)はアルゴリズム上無視できない要素の一つです。具体的には「フォロー数に対してフォロワー数が極端に少ない」ようなアカウントは評価が低くなり、おすすめに表示されにくくなる傾向があります。これは大量フォローで無理にフォロワーを増やそうとするスパム的行為を抑制する意図があると考えられます。
極端な例を挙げれば、1000アカウントをフォローしてフォロワーが100人しかいないようなケースです。この場合、フォロー数過多・フォロワー少数でFF比0.1と低く、「フォロー返し狙いの質の低いアカウント」と判断されかねません。アルゴリズムはこうしたアカウントの投稿をおすすめタイムラインで露出しにくくしています。逆にフォロワーの方が多い状態、例えばフォロー300・フォロワー1000(FF比3.3)のようなアカウントは「影響力がある(他者からフォローされる存在)」とみなされ、有利に働きます。
ただし注意点として、フォロワー数自体は絶対的な指標ではありません。2023年以降のアルゴリズムでは「フォロワーが少なくても質の高いコンテンツは上位表示される」流れも出てきています。実際、TikTok的なアルゴリズム化により、フォロワー0でもバズるケースがTwitterでも見られるようになりました。したがってFF比は不自然でなければ気にしすぎないことも大事です。変にフォローを増やしすぎず、自然増のフォロワーによって結果的にFF比が良くなるのが理想です。
要は、フォローもフォロワーも「質」を重視しましょうということです。興味のないアカウントを闇雲にフォローするのではなく、自分に関連する情報源だけをフォローし、フォロー返し狙いの無差別フォローは避けましょう。そうすればフォロー数は必要最低限に抑えられます。一方フォロワーも、懸賞目当ての一時的なフォロワーより長期的に関心を持ってくれるフォロワーを増やす方が、結果的にアルゴリズム評価を高めてくれます。
まとめると、FF比は健全な範囲に収めるのがベターです。理想はフォロワー数 >= フォロー数であり、少なくともフォロー数がフォロワー数の何倍もある状態は早めに解消した方が良いでしょう。もし過去に大量フォローしてしまっているなら、エンゲージのないアカウントを整理して適正化することをおすすめします。
まとめ|アルゴリズムを理解してTwitter Xを伸ばす
仕組みを知ることが伸びの第一歩
以上、Twitter改めXのアルゴリズムについて、その仕組みから評価ポイント、最新動向まで幅広く解説しました。
最後に要点を整理すると、アルゴリズムの仕組みを知り、それに沿った運用をすることがアカウント成長の第一歩です。闇雲に投稿して「伸びないなあ…」と嘆くのではなく、なぜ伸びないのかデータやルールの面から分析し、施策を講じることが重要です。
Xのアルゴリズムは日々アップデートされていますが、その根底にあるテーマは一貫しています。「ユーザーに長く使ってもらえる良質なコンテンツを届ける」これに尽きます。
つまり運用者としては、アルゴリズムを敵視するのではなくユーザーにとって価値ある投稿を追求することで、結果的にアルゴリズムにも評価されるという好循環を目指すべきです。「How can I trick the algorithm?(どうすればアルゴリズムを出し抜けるか)」ではなく、「What does the algorithm want?(アルゴリズム=ユーザーは何を求めているか)」の視点が大切です。
本記事で触れたエンゲージメント重視や滞在時間、ネガティブ回避、メディア活用、AI時代の質の追求などのポイントは、今後も大きく変わらないでしょう。
細かな仕様変更はあっても、結局は「ユーザー本位の情報発信」が最強のアルゴリズム対策であることに変わりはありません。
まずはアルゴリズムの基本原理を踏まえ、自分の運用スタイルを見直すところから始めてみてください。それが伸び悩みを打破する第一歩となるはずです。
戦略的な運用でビジネスにも活かせる
アルゴリズム理解に基づく戦略的な運用は、単にフォロワー数を増やすだけでなくビジネス成果にも直結します。
なぜなら、フォロワーが増えてエンゲージメントが高まるということは、それだけ自社の情報発信力が高まり見込み顧客との接点が増えるということだからです。
実際、Twitter(X)を上手く伸ばしたことで売上や問い合わせ数が大きく向上した企業も数多く存在します。
例えば、アルゴリズムに最適化した投稿でバズを生み出せば、一夜にして自社商品が数万人に知られ大ヒットする可能性もあります。
継続的に有益な情報を発信しエンゲージメントを蓄積すれば、信頼性の高いブランドイメージが形成され、競合他社との差別化にもなります。
SNSマーケティング担当者にとって、Xのアルゴリズム攻略は現代のデジタル戦略の重要な一ピースと言えるでしょう。
そのためには本記事で述べたような総合的なアプローチが求められます。
プロフィールから投稿内容、タイミング、ファンとの対話、分析と改善まで、トータルでプランニングしていくことが成功への道です。
幸い、Xは他のSNSに比べて拡散力が強く、一度波に乗れば大きなリターンが得られるプラットフォームです。
「アルゴリズムが味方になれば数万人規模にリーチするのも夢ではない」この可能性がある以上、チャレンジしない手はありません。
今日からできる実践ポイントとしては、次の3つが挙げられます。
- 仲間づくり: 他のユーザーの投稿に積極的にいいねやコメントをして、コミュニケーションを取れる仲間を増やす。交流が増えれば関連ユーザーとしてお互い表示されやすくなる。
- メディア活用: なるべく画像や動画を付けて投稿する習慣をつける。視覚情報でユーザーの関心を引き、滞在時間を伸ばす。
- 分析と改善: 自分の投稿や業界でバズっている投稿を定期的に分析し、何が良かったのかを学ぶ。そしてその知見を次の投稿作りに活かして質を高める。
地道なようですが、これら基本を愚直に続けることが、最終的に大きな成果につながります。
アルゴリズムは常に進化しますが、だからこそ本質を押さえた運用をしていれば多少の変化にも揺るがなくなります。
ぜひ本記事を参考に、アルゴリズムと上手に付き合いながらX運用を成功へ導いてください。 あなたのビジネス目的に合った成果が得られることを願っています。



-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-2-300x169.png)
-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-1-300x169.png)
-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-300x169.png)
-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-5-300x169.png)
-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-4-300x169.png)
-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-2-300x169.png)
-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-3-300x169.png)
-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-300x169.png)
コメント