X(旧Twitter)で炎上したときの対応方法とは?NG行動と正しい対処法を徹底解説【2025年最新】
X(旧Twitter)では、たった1つの投稿が一晩で何万人にも拡散され、企業や個人の信用を一気に失わせる「炎上」が起こることがあります。
その火種は、不適切な発言や誤解を招く表現、あるいはアカウント運用ミスなど、思わぬところから生まれます。
本記事では、炎上の仕組みや起こりやすい理由、具体的な対応ステップ、そして日頃からできる予防策までを網羅的に解説します。
 田代
田代SNS運用担当者はもちろん、個人ユーザーにとっても、炎上のメカニズムを理解し、適切な対応方法を知っておくことは、信頼を守るための必須スキルです。
このガイドを読めば、もしもの時に慌てず対応できるだけでなく、炎上そのものを未然に防ぐ力も身につきます。
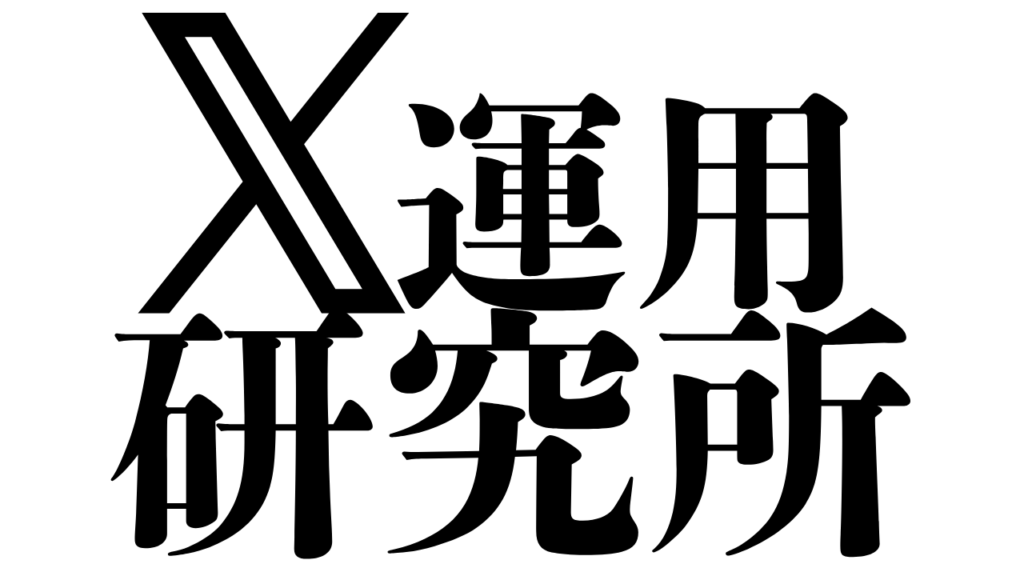
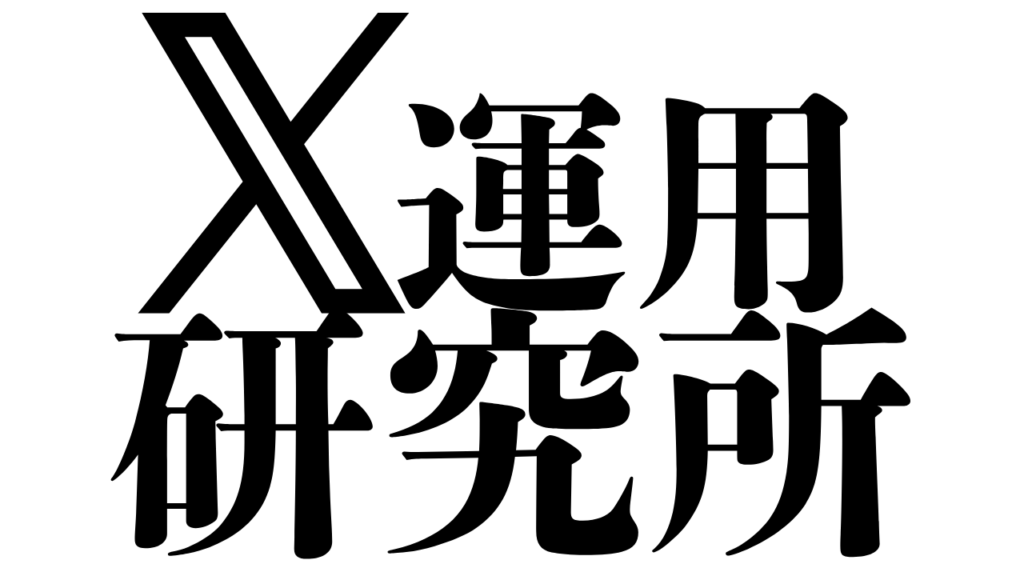
X運用研究所は、Momemtum Marketingが運用する、X運用ノウハウを体系的に学べるオウンドメディアです。
SNSを“ただの発信手段”から、“価値を生み出す武器”へ。
このメディアは、すべてのXユーザーの可能性を広げる研究と実践のプラットフォームです。
X道場 ~for Bussiness~
X(旧Twitter)は、単なる情報発信ツールではなく、大きな成果をもたらす強力なマーケティングプラットフォームです。
弊社のサービス「X道場」では、フォロワーを増やすだけではなく、ビジネス目標に直結する本質的なXマーケティングを実践します。企業様から一般ユーザーまで幅広く使用いただけるプラットフォームです。


そもそも「炎上」とは? X(旧Twitter)で起こる原因とメカニズム
X(旧Twitter)における炎上とは?定義と種類をわかりやすく解説
SNSにおける「炎上」とは、ネット上の投稿に批判や中傷のコメントが殺到し、手に負えない状態になることです。
コメント欄が批判的な意見で埋め尽くされ、発信者や企業のイメージが大きく損なわれてしまいます。
誰でも気軽に発信できるSNSだからこそ、一度火が付くと一気に広がりやすいのが特徴です。
炎上にはいくつかパターンや種類があります。
それぞれ原因や経緯が異なりますが、共通して「投稿内容への否定的反応」が引き金となります。
主な炎上の種類を分類すると、例えば次のようなものがあります:
- 失言・不適切発言型:SNSで不用意または不適切な発言をしてしまい批判を浴びるケースです。道徳や倫理に反する内容、社会通念に照らして非常識な発言は大炎上を招きがちです。
- 誤爆・アカウント間違い型:担当者が個人アカウントと勘違いして企業公式にプライベート投稿をしてしまうケースです。突然関係ない内容が公式から発信されるとフォロワーは混乱し、その投稿が不適切なものであれば一気に拡散・炎上します。
- 拡散・暴露型:SNS外で起きた企業の不祥事や商品トラブルが、利用者の投稿をきっかけに一気に広まるケースです。例えば商品の欠陥や店舗での不適切対応がユーザーによって暴露され、それがRT(リポスト)で拡散して炎上することがあります。
- 誤解・ミスリード型:投稿内容が誤解を招いて炎上するケースです。本人に悪意はなくても、文脈不足や表現のミスにより受け手に違う意味で伝わってしまい批判が集まることがあります。
- ステルスマーケティング型:広告であると明示せずインフルエンサー等に商品PRさせる「ステマ」が発覚して炎上するケースです。第三者を装った宣伝行為はユーザーの信頼を裏切り、企業・起用したインフルエンサー双方が激しい批判にさらされます。
なぜ、X(旧Twitter)では炎上が起きやすいのか?構造的な理由
X(旧Twitter)は拡散力が極めて高く、短時間で投稿が多人数に届く仕組みになっています。
そのため、炎上が起こりやすく広がりやすい構造を持っています。
具体的には以下のような点が挙げられます。
- リポスト(リツイート)と引用リポストによる爆発的拡散:Xでは誰かの投稿を簡単にリポストでき、さらに自分のコメントを付けて引用リポストすることも可能です。他人の批判的コメント付きで投稿が共有されると、それを見た人がさらに反応し、雪だるま式に拡散が進みます。次々に他者を巻き込み、「バズ」のような状態にまで膨れ上がるのです。
- アルゴリズム(おすすめ表示)の特性:従来のTwitterアルゴリズムは、エンゲージメント数(反応の多さ)を重視する傾向がありました。そのため批判的なコメントが集まっている投稿でも、「注目を集めている=有益なコンテンツ」と判断されてタイムライン上で拡散されてしまう側面があったのです。実際、怒りやヘイトなど人々の感情を強く刺激する投稿ほど「反応が多い」ためアルゴリズムに好まれ、結果的に炎上が拡大する構造が指摘されています。しかし2023年以降、Xには高度なAI(Grok)の導入が進み、ネガティブな炎上投稿を過剰に拡散しないよう改善が図られています。
- 「バズり」狙いと過激化:多くのユーザーに見てもらおうと、企業・個人問わず注目狙いの投稿が増えがちです。面白さや話題性を優先するあまり配慮を欠いた内容を投稿し、炎上してしまうケースが後を絶ちません。
- 匿名性とリアクションの過熱:Xはユーザー名をニックネームにでき匿名性が高いため、直接顔が見えない安心感から過激な批判を書き込みやすい側面があります。また炎上状態では「自分も何か言わなければ」と感情的なリアクションが次々と投稿され、批判がエスカレートしがちです。
炎上の火種になりやすいX(旧Twitter)での投稿例と共通点
どういった投稿が炎上を招きやすいのか、炎上しやすい投稿パターンと問題にならない投稿を比較してみましょう。
炎上の火種になりがちな投稿には、いくつか共通するポイントがあります。
| 炎上しやすい投稿パターン | 問題になりにくい投稿パターン |
|
感情的で攻撃的な表現(特定の個人や集団への誹謗・差別)
例:競合他社の商品を「価値ゼロ」と酷評する |
丁寧で配慮ある表現(批判ではなく提案や中立的意見)例:「他社製品にも良い点がありますが、当社製品は~です」といった説明
|
|
社会的にセンシティブな話題に無神経に触れる
例:大事故直後に冗談めかした投稿をする |
時事ネタには慎重な姿勢で臨む
例:社会的事件に関しては軽率な発信を避け、情報発信は公式声明に留める |
|
企業公式で個人的主張・私情を発信
例:担当者が自社公式アカウントで他社や顧客を批判する |
公式アカウントでは公的な情報のみ発信
例:サービス案内やお知らせ等、個人の感情を交えない投稿 |
|
真偽不明の情報・デマの拡散
例:裏付けのない噂話を引用して意見を述べる |
信頼性の確認された情報のみ共有
例:公式発表や信頼できるニュースソースを引用して発信する |
|
ステルスマーケティングや炎上商法
例:広告と明記せず商品を褒める投稿、過激発言で注目を集めようとする |
誠実で透明性のあるマーケティング
例:「PR」表記をした上で商品の特徴を紹介する投稿、ユーザーに有益な情報提供を心がける |
このように、不用意な表現や配慮不足・公式と私情の混同・悪質な意図(隠匿広告・挑発)などが重なる投稿は炎上リスクが高まります。
一方で、内容と表現に十分注意し、ユーザー視点で「不快に感じる人がいないか」を考えた投稿は炎上しにくくなります。
投稿前に自分の書いた内容を客観視し、上記の比較表の右側のような姿勢で発信することが大切です。
X(旧Twitter)で炎上時にやってはいけないNG対応とは?
X(旧Twitter)では、放置・スルーは逆効果?沈黙が招くさらなる火種
炎上に気づいていながら「何もしないで様子を見る」のは基本的にNGです。
対応を怠って沈黙している間にも批判は拡散し続け、状況は悪化の一途をたどります。
実際、SNS炎上は対応が遅れるほど収拾がつかなくなり、企業イメージも悪化します。
多くのユーザーは沈黙を「無視」「反省していない」と受け取り、さらに怒りを募らせる傾向があります。
ただし一部には、内容次第で「下手に動かず静観した方がよい場合」もあります。
例えばサービスの良し悪しなど主観の問題でユーザー間議論が起きている場合、公式が下手に首を突っ込むと火に油を注ぐ恐れがあるのです。
このような場合は迂闊に反応せず経過を見る勇気も必要とされています。
ポイントは見極めで、明らかに自社に非があるケースや間違った情報が広まっている場合は、沈黙せず速やかに謝罪・訂正するべきです。
一方、意見の相違程度であれば過剰反応しない方が鎮静化しやすいとも言われます。
(ある調査では、多くの炎上は約72時間以内に沈静化するとのデータもあります)
要するに、「放置=常に悪」ではないが、基本は迅速な初動対応が求められると覚えておきましょう。
放置が許されるのは非常に限定的なケースであり、多くの場合は沈黙せず誠実に向き合う姿勢が重要です。
逆ギレ・挑発・開き直りにもリスクが存在する
炎上対応で絶対に避けるべきは「逆ギレ」や「開き直り」です。
批判されて悔しい気持ちから反論したり、感情的にユーザーに噛みついてしまう対応は、火に油どころかガソリンを注ぐような行為です。
専門家も「謝罪の際には真摯な態度が求められるのは言うまでもなく、逆ギレや開き直りはもってのほか」と指摘しています。
例えばユーザーの批判に対し「そんな批判をする方がおかしい」といった防衛的・挑発的な発言をすれば、さらなる怒りを買って炎上は加速します。
企業アカウントであれば一瞬で信用を失い、個人であってもネット上に悪評が残り続けるでしょう。
また、言い訳がましい対応もNGです。
例えば「「我々はそんなつもりではなかったのですが…」」などと弁明すると、「受け取った側の問題だ」と言っているように聞こえてしまいます。
結果として批判したユーザーの感情をさらに逆撫でし、炎上が長引く原因になります。
「自分は悪くない」「誤解だ」と主張したくても、炎上中はグッとこらえて非を認める姿勢が大切です。
開き直りも論外です。「何が悪いんだ」と開き直ったり、冗談めかして済ませようとすると、世間は「反省していない」とみなし厳しい態度を取ります。
過去には炎上した有名人が半笑いで釈明会見を行い、余計に批判を浴びた例もあります。炎上時は終始低姿勢かつ誠実に徹しなければなりません。
安易な削除・アカウント非公開がもたらす印象悪化
炎上した投稿をすぐに削除することも、場合によっては逆効果です。
「批判が増えたからとりあえず消そう」という安易な削除は、ユーザーから「消して逃げた」と受け取られます。
実際、ネット上では投稿を削除しても魚拓(スクリーンショットやコピー)が瞬く間に出回り、「隠蔽する気か」とさらなる炎上を招く可能性があります。
何も説明せず消すのではなく、削除する場合も「●月●日の投稿について不適切でしたので削除いたしました」と経緯を説明することが重要です。
同様に、炎上直後にアカウントを非公開(鍵アカ)に切り替えたり、一時的に閉鎖したりするのも印象は良くありません。
批判から逃げたように見えてしまい、かえって外部で憶測や批判が飛び交うことがあります。
特に企業公式アカウントが鍵をかけると報道沙汰になるケースもあり、得策ではないでしょう。
削除や非公開対応はタイミングとやり方が難しく、慎重に行う必要があります。
炎上の原因や状況をしっかり把握した上で、「謝罪を発表した後に問題投稿を削除する」など適切な順序で行うことが大切です。
謝罪や説明なしに消すと「責任放棄」と捉えられがちなため、必ず周囲への説明とセットで対処しましょう。
X(旧Twitter)での炎上時に取るべき正しい対応ステップ
X(旧Twitter)では、状況把握と初動の冷静な対応がカギ
炎上してしまった際は、何よりも慌てず冷静になることが肝心です。
その上で、以下の初動ステップを迅速に踏みましょう。
- 事実関係の確認(状況把握):まず「何が起こっているのか」「原因は何か」「SNS上でどんな反応が多いか」を速やかに確認します。炎上の発端となった投稿や、拡散している批判内容をスクリーンショット保存し、時系列で整理しましょう。この時点で焦って謝罪文を出すのは厳禁です。原因を取り違えたまま謝罪すると論点がずれていて「誠意がない」と再批判される恐れがあります。冷静に炎上の本質を把握することが最優先です。
- 社内報告・共有:状況が掴めたら、すぐに上司や関係部署に報告します。担当者の独断で動かず、チームで対応方針を検討しましょう。炎上は企業全体や関係者に影響を及ぼすため、社内で迅速に情報共有し、広報チーム・経営陣・法務部門などと連携して対応を協議することが不可欠です。誰が責任者となり、どのようなメッセージを出すかなど、組織的に判断します。
- 初期対応の方針決定:事実確認と社内協議を経て、「公式に反応すべきか静観すべきか」「謝罪が必要か」など対応方針を決めます。批判が事実に基づくなら謝罪と訂正を行うべきですし、誤解が原因なら誤解を解く説明が要るでしょう。対応しない方が良いケース(前述の静観が有効な場合)でも経過観察と記録は続け、機を見て対応できる準備はしておきます。
以上のような初動を迅速かつ的確に行うことで、被害拡大を防ぎ信頼回復の一歩目を踏み出せます。
初動対応が遅れるとその遅れ自体が批判材料になるため、「異変に気づいたら即共有・即対応開始」が鉄則です。
X(旧Twitter)における、適切な謝罪と説明のポイント
炎上対応の中核は謝罪と再発防止策の説明です。
ここでの対応次第で、むしろ世間から評価される場合もあれば、逆に二次炎上してしまう場合もあります。
適切な謝罪を行うためのポイントを押さえましょう。
- タイミング:状況把握後、対応方針が決まったらできるだけ早く公式対応を発表します。ただし原因を理解せずとりあえず謝罪するのはNGなので、事実確認と社内協議に必要な時間は確保します。その上で「まずはお詫び申し上げます。現在詳細を調査しております」といった一次謝罪を速やかに出すのも有効です。
- 誠意と非の明確化:謝罪文では何が問題であったかを具体的に認め, 自社(自分)の非をしっかり明言します。「不適切な表現がありました」とぼかすのではなく、何がどう不適切だったのかを説明しつつ謝罪します。例えば「弊社担当者の◯◯という発言が配慮を欠いておりました。深くお詫び申し上げます」のように、問題の核心に触れることが大切です。
- 「ご不快に感じたら…」は禁止:「もし不快に感じた方がいたらお詫びします」という形式の謝罪文は一見丁寧ですが、実は典型的な悪い謝罪例です。これは「不快に感じた人がいるなら謝るけど、こちらに非はない」という含みが透けて見え、かえって反感を買います。謝罪すべきは相手の感情そのものではなく、自らの不適切な行為であると理解しましょう。したがって「◯◯という不適切な投稿をし、ご不快な思いをさせました。申し訳ありません。」と行為自体を謝罪する表現が必要です。
- 言い訳をしない:謝罪文中に理由説明を入れる際も、決して自己弁護にならないよう注意します。「○○のつもりだった」「悪意はなかった」といった言い訳は一切不要です。ユーザーからすれば理由は関係なく、結果として問題が起きたことが重要だからです。どうしても背景説明が必要な場合でも、「弁解ではなく説明」と断ったうえで簡潔に述べ、すぐ謝罪と改善策の話に移るのが望ましいです。
- 再発防止策の提示:単なる謝罪だけでなく、「今後同じ過ちを繰り返さないための対策」を必ず示します。例えば「SNS投稿ルールを見直し、担当者への教育を強化します」「チェックフローを導入します」など具体策を明記しましょう。炎上の事実は消せませんが、「二度と起こさない姿勢」と「具体的行動計画」を伝えることでユーザーも納得しやすくなります。
- 形式より心を:テンプレートに頼らず、自分の言葉で心からの謝罪を書くことが重要です。コピペのような定型文では誠意が伝わりません。「申し訳ございませんでした。」の一文にも気持ちを込め、必要に応じて謝罪会見や動画メッセージなど伝わりやすい方法も検討します。
以下に良い謝罪文と悪い謝罪文の例を比較してみます:
| 良い謝罪文の例 | 悪い謝罪文の例 |
|---|---|
| この度、弊社公式Xアカウントにおいて配慮を欠いた発言(○○)があり、多くの皆様を不快にさせてしまいました。当該投稿は弊社の至らなさによるものであり、深くお詫び申し上げます。現在、内部調査を行うとともに、再発防止策として社内SNS運用ルールの徹底を開始しております。今後このようなことが二度と起こらないよう全社で取り組んで参ります。 | もし今回の投稿で不快に感じた方がいらっしゃいましたら、お詫び申し上げます。(※問題の具体的言及なし)私どもとしては悪気はなく良かれと思ってやってしまったのですが、このような結果となり残念です。(※言い訳がましい)皆様にご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。(※再発防止策の言及なし) |
良い謝罪文では何が悪かったかを具体的に認め、全面的に非を認めた上で再発防止策に言及しています。
一方、悪い例では「不快に感じたら~」という表現や弁解が含まれ、何について謝罪しているのか曖昧です。
炎上対応では前者のような誠実な謝罪を心がけましょう。
ステークホルダー(関係者)への影響と連携の取り方
炎上は当事者だけでなく、周囲の様々なステークホルダーにも影響を及ぼします。
企業であれば社員・株主・取引先・顧客、個人であっても家族や所属組織などが関係してくる可能性があります。
したがって、炎上時には関係者への配慮と連携も忘れてはいけません。
社内の連携:前述したように、炎上が発覚したら速やかに上層部や関連部署に報告します。
特に広報・PR担当とは二人三脚で対応する必要があります。
外部発表用の謝罪文は広報の知見を借りつつ、トーンや内容を検討しましょう。
また、法務部門とも相談し、謝罪表現や対応策が法的に問題ないかチェックを受けます(例えば賠償等が絡む場合の表現など)。
カスタマーサポート部門がある場合、炎上に関連した問い合わせが殺到する可能性が高いため、状況と対応方針を共有しFAQを用意するなど備えます。
炎上内容によっては、社外の関係者への説明が必要となります。例えば、取引先企業やスポンサー、業界団体などにも説明・謝罪などです。
自社だけでなく他社の商品や人物が関わる炎上(例:他社批判ツイートで競合に迷惑をかけたケースなど)では、早めに先方に連絡し事情説明とお詫びをしましょう。
メディアに取り上げられる規模なら、プレスリリースを出して公式見解を示すことも検討します。
直接被害を受けた人への対応:炎上によって特定のユーザーが被害者となっている場合(たとえば不適切対応でクレームを寄せたお客様本人等)、その方には個別に直接連絡を取り謝罪することも重要です。
公開の場での謝罪に加え、被害当事者へは誠意を持って補償やお詫びを行うことで、かえって信頼回復につながることもあります。
記録と教訓の共有:炎上対応が一段落したら、今回の経緯と対応を社内で振り返り共有しましょう。
問題点や良かった点を整理し、関係者間で教訓とします。必要に応じて社内ガイドラインやマニュアルを改訂し、再発防止に活かします。
企業・個人で異なる炎上リスクと対応スタンス
企業アカウントの場合の注意点とガイドライン整備の重要性
企業公式アカウントはその企業の「顔」であり、炎上すれば自社ブランド全体に大きな打撃を与えます。
企業アカウントが炎上しないため、そして万一炎上しても被害を最小限に抑えるためには、平時からのルール整備と体制構築が不可欠です。
- SNS運用ポリシー・ガイドラインの策定:企業としてSNSをどう運用するか、事前に明確なガイドラインを設けます。「投稿内容の基準」「口調と言葉遣い」「絶対に避ける話題・表現」「投稿の頻度とタイミング」などを定めておき、担当者全員が遵守します。特に「絶対にしてはいけないこと」を明文化して共有しておくと、炎上リスクを大幅に下げられます。ルールがあれば担当者が変わってもブレが減り、一貫したブランド発信につながります。
- 投稿前のダブルチェック体制:ヒューマンエラーを防ぐため、投稿は必ず複数人で確認する仕組みにします。担当者が草案を作成し、別のスタッフや上長が内容・表現をチェックしてから投稿するフローです。これにより、独断や思い込みによる不適切投稿(誤爆含む)を防ぎます。実際、重大炎上の多くはチェック不足の「うっかりミス」なので、複数人の目で見るだけでもリスク低減に効果的です。
- 炎上対応マニュアルの整備:炎上発生時にどう対処するかをまとめたマニュアルを作成しておきます。初動の手順(誰に報告し、どうチームを招集するか)、社外発表のプロセス、テンプレート(謝罪文の構成例)などを事前に用意しておけば、いざという時に慌てず対応できます。特に中小企業では「マニュアルは必ず必要。担当者レベルでパニックに陥らないためにも整備を」と専門家も指摘しています。
- 投稿承認フローと管理ツール:可能であればSNS管理ツールを導入し、承認ワークフローを組み込むのも有効です。投稿前チェックリストをデジタル化したり、投稿予約機能で誤タイミングを防ぐなど、テクノロジーの力も借りてリスクを下げます。特に複数人で運用している場合、誰がどの投稿を担当したかログを残すことも大切です。
- 社員教育と意識向上:企業全体でSNS炎上リスクへの感度を上げるため、研修や勉強会を実施します。SNS担当者だけでなく、一般社員やアルバイトにもモラルとリテラシー教育を行いましょう。一人ひとりが当事者意識を持つことで、うっかり不適切投稿をする社員も減ります。実際、社員の私的投稿が原因で企業が炎上するケース(いわゆる「バイトテロ」)も多いため、広く教育しておくことが重要です。
以上のような対策により、企業として炎上リスクをかなりコントロールできます。
それでもゼロにはできませんが、備えあれば憂いなしです。
実践的なガイドラインとマニュアルがあれば、万一炎上しても冷静に対応でき、信頼回復も早まるでしょう。
個人アカウントが巻き込まれたときの身の守り方
個人で炎上してしまった場合も基本的な対応は企業と大きく変わりませんが、自分自身を守るために注意すべき点があります。
個人の炎上は精神的負担も大きいため、冷静な対応と身を守る工夫が必要です。
- 落ち着いて現状把握
まずは深呼吸し、何が原因で炎上しているのか事実を整理します。
感情のまま反論ツイートなどすると事態が悪化するので、ぐっとこらえて状況を確認します。
可能なら信頼できる友人や同僚に相談し、客観的な視点でアドバイスをもらうのも良いでしょう。 - アカウント設定の見直し
炎上の矢面に立たされている間、一時的にプライバシー設定を強化することも検討します。
具体的には、見知らぬ人からの返信を減らすためにツイート毎にリプライ制限をかけたり(投稿時に「フォローしている人のみ返信可」等に設定)、通知設定を変えてフォロー外からの通知をオフにするなどです。
場合によっては鍵アカウント化(非公開)することで新たな拡散を防ぐ手もあります。
ただし、既に拡散している内容は止められない点に留意し、非公開にするかは慎重に判断しましょう(非公開化がニュースになる場合もあります)。
鍵アカウントに関しては、こちらの記事で詳しく説明をしているので、鍵垢の定義や設定方法はコチラを参照ください。
-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-4-300x169.png)
-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-4-300x169.png)
- 直接的な反論や批判合戦をしない
個人の炎上では、つい自分を守ろうとして他者と言い争いたくなるかもしれません。
しかしネット上で言い争うとさらに悪化する可能性が高いです。
相手を論破しようとするほど相手も攻撃的になり、第三者も参戦して泥沼化します。
反論したい気持ちは抑え、必要最低限の説明や謝罪に留め、それ以上は発信しない勇気も大切です。 - 必要なら謝罪・訂正する
自分に明らかな非がある場合は、早めに謝罪した方が収束しやすいです。
個人アカウントでも、簡潔に経緯説明と謝罪ツイートを固定表示するなどして誠意を見せましょう。
「言い訳じみたことは一切書かない」点は企業と同様で、素直に謝ることが炎上沈静化に有効です。
反対に自分に非がないデマ炎上の場合は、焦って謝罪すると認めたように誤解される恐れもあるため、慎重に対応します。
(その場合は事実と異なる旨を穏やかに説明し、あとは静観する方が良いこともあります) - 誹謗中傷への対策
炎上すると関係ない誹謗中傷まで飛んでくることがあります。
あまりに酷い侮辱や脅迫など違法の可能性がある投稿については、記録(スクショ)を残し、法的手段も検討してください。
具体的には「殺すぞ」「○○してやる」といった明確な脅迫、根拠のない犯罪者扱いなどは名誉毀損・脅迫罪に該当し得ます。
そうした投稿は無視せず、警察相談や弁護士への相談を視野に入れましょう。
すべてのケースで警察が動くとは限りませんが、相談実績を作るだけでも次回の対応がスムーズになる利点があります。 - メンタルケア
個人で炎上を経験すると精神的ダメージは大きいものです。
必要なら一旦SNSから離れて心を落ち着けることも大切です。信頼できる人に話を聞いてもらったり、専門家(カウンセラー等)に相談することも検討してください。
炎上は一時の出来事であり、自分の全人格を否定されたわけではないと捉えるようにしましょう。
拡散や二次被害を最小限に抑えるSNSの設定とは?(鍵垢、リプ制限など)
炎上時やその予防策として、SNSプラットフォーム側の設定機能を活用することも効果的です。
X(旧Twitter)には、投稿の拡散や被害を抑えるための様々な機能がありますので、状況に応じて使いこなしましょう。
- リプライ制限:
投稿ごとに「誰が返信できるか」を設定できます。
例えば炎上中の謝罪ツイートには「フォローしているアカウントのみ返信可」に設定すれば、見知らぬ大量のユーザーから批判リプが殺到するのを防げます。
第三者による横槍を減らし、冷静な対話がしやすくなる利点があります。 - ミュート機能(キーワード・アカウント):
特定のキーワードをミュートすれば、その単語を含む通知やタイムライン表示を見えなくできます。
炎上中に特定のスラングやハッシュタグで誹謗中傷されている場合、一時的にミュートすることで精神的負担を軽減できます。
また、執拗に絡んでくる特定アカウントをミュートまたはブロックすれば、そのユーザーからの通知が来なくなります。
ただしミュート・ブロックしても相手側からは投稿閲覧や引用は可能なので、「自分が見えなくする」ための機能と割り切りましょう。 - 非公開アカウント(鍵アカ):
アカウントを非公開に設定すると、新たなフォロワー以外には自分のツイートが見えなくなります。
炎上拡散のスピードを抑えるには有効ですが、既に拡散した投稿までは消せません。
また非公開化した事実が周知されると「逃げた」と捉えられるリスクもあります。
一時避難的措置としては有用な場面もありますが、慎重に判断してください。 - 通知フィルター:Xには通知タブで「品質フィルター」をオンにしたり、フォローしていない人からの通知をオフにする設定もあります。
炎上で心ないリプライが大量に飛んでくる際、一時的にこれらを設定すれば、攻撃的な通知を目にしなくて済みます。
加えて、新規アカウントやプロフィール未設定の怪しいアカウントからの通知を除外するオプションもあるため、荒らし対策になります。 - コメントオフ機能(コミュニティノートや制限付き投稿):
現在Xには投稿への直接コメントを完全にオフにする機能はありませんが、代替的にSpaceやNotesなど他機能を活用する方法もあります(例えばNoteへの謝罪文掲載し、Xではリンク共有のみ行う等)。
また最近はコミュニティノートで補足説明を付けるなど、新機能も増えているため、適切に利用しましょう。
これら設定を使うことで炎上時の被害を「見えなくする」「広げない」効果が期待できます。
ただし、根本的な解決策ではなく補助的なものですので、本質的な謝罪・説明対応と併用する形で活用してください。
よくある質問|炎上対応のQ&A



炎上が自然に収束するまで放置しても大丈夫?
- 炎上が自然に収束するまで放置していようと思うのですが、大丈夫でしょうか?
-
ほとんどの場合、放置はおすすめできません。
確かに「多くの炎上は72時間程度で沈静化する」というデータもあり、内容によっては静観が正解なケースもあります。しかしそれは稀な例で、特に自社や自分に明確な非がある場合は放置厳禁です。
沈黙は「無視」「反省なし」と受け取られ、批判が増幅するのが通常です。事実誤認が広まっている場合も、放置すれば誤情報が定着しかねません。
例えば単なる意見の食い違い程度なら議論が勝手に落ち着くこともありますが、
企業不祥事や差別的発言など重大なものは公式対応なしに鎮火することは期待できません。基本は速やかに誠意ある謝罪や訂正を行うのが安全策です。
その上で、一部悪質なユーザーには直接反応せず、全体への声明という形で対応すると良いでしょう。
弁護士や法的措置を取るのはどんなとき?
- 炎上してしまったのですが、弁護士への相談や法的措置を取るのは、どんなときが望ましいでしょうか?
-
炎上に伴う書き込みが明らかに違法な誹謗中傷や脅迫を含む場合、法的措置を検討すべきです。
例えば「殺すぞ」「家を燃やすぞ」といった命の危険に関わる脅迫や、根拠なく「前科がある」と書き立てるような名誉毀損的投稿、執拗な人格否定(「バカ」「ブス」など繰り返す侮辱)等は、刑事事件になり得るケースです。
このような投稿が確認されたら、証拠を保存した上で警察に相談してください。
警察がすぐ動くかはケースによりますが、相談実績を作っておくことで次回以降相談しやすくなるメリットもあります。
また、自分や自社への誹謗中傷が匿名掲示板などで続いている場合、弁護士に相談して発信者情報開示請求や投稿削除依頼の手続きを取ることもできます。
法的に訴えるか迷うラインの中傷についても、専門家の意見を聞けば対処法が見えてくるでしょう。
要するに、「批判」か「違法な中傷」かを見極め、後者であれば遠慮なく法的措置を検討してください。
特に人身の危険がある場合は迅速に警察へ相談し、身の安全を確保することが第一です。
過去の投稿から炎上する可能性を防ぐ方法は?
- 過去の投稿から炎上してしまう可能性もありますが、防ぐ方法はありますか?
-
定期的な過去投稿の見直し(セルフパトロール)が有効です。
近年、数年前の投稿が突然掘り起こされて炎上するケースも増えています。
例えば2012年頃の差別的ツイートが原因で、後年アニメ化作品が中止に追い込まれた例もありました。
過去に自分や自社が発信した情報の中に「火種」が潜んでいないか、洗い出しておく必要があります。
具体的な対策としては:
- 問題投稿の削除または非公開化:過去ログを遡り、不適切な発言・プライバシー情報が含まれる投稿は事前に削除しておきます。特に若い頃に深く考えず投稿した内容などは要注意です。企業公式の過去投稿も同様にチェックし、危険なものは整理しましょう。
- 定期的なキーワード検索:自分のアカウントの過去投稿を、差別用語や不謹慎な単語で検索してみます。思わぬ投稿が引っかかるかもしれません。Twitterの高度な検索機能を使えば、自分のアカウント+キーワードで簡単に見つけられます。
- 炎上事例の学習:日頃から他社や有名人の炎上事例をウォッチし、「どういう表現が炎上したのか」を知っておくと、自分の過去発言を見直すヒントになります。社会の価値観は変化するため、昔は許容されていた表現が今はアウトということもあります。常に最新の感覚でチェックしましょう。
- 投稿の有効期限設定:プラットフォームによっては一定期間で投稿を自動削除する機能や、投稿を期間限定公開にする設定もあります(X自体にはありませんが、サードパーティのサービスで実現可能です)。常に投稿を蓄積し続けるのではなく、ある程度古くなった投稿は整理する運用も検討できます。
- カレンダーに要注意日を登録:過去の大災害や事件の日にうっかり不謹慎と受け取られる投稿をしないよう、チームのカレンダーに「◯月◯日 注意(例:震災の日)」などと共有しておく方法もあります。これは未来の投稿についてですが、「〇年後のこの日、この投稿は問題になるかも」という視点で振り返ることにもつながります。
- 問題投稿の削除または非公開化:過去ログを遡り、不適切な発言・プライバシー情報が含まれる投稿は事前に削除しておきます。特に若い頃に深く考えず投稿した内容などは要注意です。企業公式の過去投稿も同様にチェックし、危険なものは整理しましょう。
万全を期すなら、専門の監視サービスに依頼して過去投稿やネット上の風評を診断してもらう手もあります。
重要なのは、「自分(自社)は大丈夫」と慢心せず、定期的に自己チェックする習慣です。
炎上は忘れた頃にやって来るものなので、過去のツイートも油断せず管理しましょう。
まとめ|X(旧Twitter)の炎上は初動と姿勢がすべて
NG対応を避け、冷静・誠実な対応を
Xでの炎上対応において何より大切なのは、パニックにならず冷静でいることです。
炎上すると周囲から批判が噴出し心が乱れますが、感情的に対応してしまえば事態は悪化するばかりです。
【逆ギレ・言い訳・放置】といったNG行動は徹底的に避け、一貫して低姿勢かつ誠実な対応を貫きましょう。
初動では素早く事実確認と社内連携を行い、的確な対応方針を立てます。
謝罪すると決めたら責任を認めた心からの謝罪を行い、再発防止策まで示します。
【火に油を注がない】よう、発言一つ一つに注意を払いましょう。ユーザーからの信頼は対応次第で回復も可能です。
炎上対応を誤れば二次炎上や信用喪失に繋がりますが、適切に対処すれば「むしろ誠実な企業(人)だ」という評価に繋がることもあります。
日頃からの予防が最大のリスク回避
ベストは炎上させないことですが、ゼロリスクはあり得ません。
それでも日頃の工夫で炎上確率を大幅に下げることは可能です。
投稿前チェックリストによるセルフ検閲、社内ガイドライン遵守、ダブルチェック体制、社員教育、そして過去投稿の棚卸しなど、予防策を積み重ねることが最大の防御になります。
また、SNS担当者は常に世間の動向にアンテナを張り、炎上しやすい話題や表現を把握しておきましょう。
他社の炎上事例から学び、自社で似たミスがないかチェックすることも有効です。さらに、万一に備えて炎上対応フローを決め訓練しておけば、いざという時スムーズに動けます。
Xの炎上は初動と姿勢がすべて――適切な準備と冷静な対応で、危機を乗り越え信頼を守りましょう。「備えあれば憂いなし」、平時の心掛けが将来のリスク回避につながります。
最後になりますが、本記事で紹介したノウハウや手順をひと目で振り返れる資料をご用意しました。


-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-11-300x169.png)
-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-300x169.png)
-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-5-300x169.png)
-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-2-300x169.png)
-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-6-300x169.png)
-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-7-300x169.png)
-の名前変更方法-表示名とユーザー名の違いも徹底解説!-3-300x169.png)
コメント